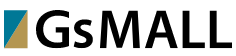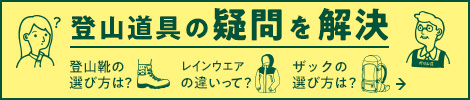日本一危険な国宝・三徳山投入堂
- 投稿者
-
本田 康之
- 日程
- 2025年05月16日 (金)~2025年05月16日 (金)
- メンバー
- イオンモール各務原店 本田
他1名
- 天候
- 晴れ
- コースタイム
- 第二駐車場(3分)受付所(11分)本堂登山参拝事務所(19分)文殊堂(3分)地蔵堂(2分)鐘楼堂(3分)観音堂(2分)投入堂(8分)文殊堂(20分)本堂登山参拝事務所(10分)受付所(3分)第二駐車場
- コース状況
- アプローチ
・車利用は国道179号から県道21号で三朝温泉経由で三徳山へ
・公共交通機関はJR倉吉駅から三徳山駐車場までバスがあります
①三徳山は受付所で入山志納金400円、投入堂受付で投入堂参拝登山料800円を納めます
②投入堂参拝受付時間は8時から15時(下山時間16時30分)、単独入山はできず、服装や靴のチェックが入ります。また配られる六根清浄のハッピ着用が必要です。
③前日に雨や当日に雨が降ると入山できませんので、ホームページで確認しましょう
⇒今回は昼から雨の可能性がありましたが、入山可能でした
④受付の先に門があり、下ったら、いきなりかずら坂と呼ばれる登りで、木の根道のような道が続きます
⑤最初に現れる文殊堂へ登る際に岩場の鎖場があります。ここは登りと下りで道が分かれています
⑥文殊堂が一番、高度感があり、お堂の木の板が細いです
⑦文殊堂からヤセ尾根のような細い岩の道が続きます。ここも登り下りで分かれます
⑧地蔵院は文殊堂に比べ。木の板が広く、文殊堂で慣れていれば、怖さはないです
⑨文殊堂の上で鐘楼堂があり、ここで鐘を1回つきます
⑩観音堂は岩場沿いを回り込む胎内くぐりがあります
⑪観音堂の先が奥の院でここが終点で、下から見上げる形になります
⑫下りは標識に従い、一部は専用道を歩きます。やはり文殊堂の下りがクサリ坂と呼ばれ、ここがポイントです。道は右左に分かれ、二人で同時に下れます。
⑬立ち寄り湯は三朝温泉に無料の河原風呂があります。旅館の一部でも1000円程度で日帰り対応しているところがあります。
- 難易度
-

感想コメント
三徳山と言った場合、投入堂(三徳山三佛寺)を指す場合が多いですが、この寺は中腹に過ぎないです。もちろん三徳山全体が境内になるわけですが、2015年には「三徳山・三朝温泉」が「日本遺産」の第一号として認定され、投入堂の名で知られる奥ノ院の建物は、中腹の断崖に浮かぶように建てられた他に類を見ない建築物で、国宝にも指定されています。断崖絶壁の上に建てられたお寺で、死亡事故が多発していることから、「日本一危険な国宝」という異名を持っています。
なお三徳山(みとくさん・899m)の山頂自体はもっと上の方にあり、この三佛寺からは登らず、南側から登ることになります。今回、昼から登るつもりでいましたが、雨が降りそうなので投入堂のみとしました。
8時からが受付開始で、8:30に通過するも先客がいるようです。登山靴で行きましたが、靴のチェックはソールになります。帰りにすれ違った方の靴を見るとスニーカーで登っている人もいて、今一つ基準がわかりません。
スタートからすぐに急な登りとなります。滑りそうな地面には土嚢袋の滑り止めが設置され、よく整備されていますが、木の根が地面に覆うような登山道でやはり登山靴が最適だと感じる所でした。
文殊堂まで来ると建物下より鎖場を登ります。ここは下りと登りが分かれていますので安心です。文殊堂は境内を一周するのですが、高台でさらに柵もなく、細いので高度感を感じることでしょう。ここで慣れると、上の地蔵堂の境内はちっとも怖くなくなります。
鐘楼堂で鐘を突いた後、細い岩場の通過辺りまでが危険個所のメインになります。
岩場の真下にある観音堂を過ぎると、もう終点の投入堂が現れます。写真でよく見る風景ですが、崖下にぱこっとはまったあの建物、どうやって造ったのか本当に不思議です。
投入堂はその直下で立ち入り禁止になっていますが、メンテナンスをするにしても命がけのように見えます。ここでいろんな角度で撮影を楽しみ、下山します。
帰りに文殊堂でもう1周してから下りましたが、結局3回ほど、回りました。
文殊堂の下りの鎖場は右左に分かれますが、右側の方が下りやすい感じがしました。ここは鎖を持てば、問題なしです。
下りはわりに早く下れました。
帰りは谷川天狗堂で栃餅を食べて、一服するとよいです。出来立てのような感じで柔らかくおいしいです。
本日の服装(春の低山)
①ウエアー
インナーは(アイスブレーカー)半袖Tシャツ
ボトムスは(マウンテンハードウェアー)3シーズンパンツ
②ギア
登山靴は(スポルティバ)「トランゴトレックGTX」、
ザックは(ブラックダイヤモンド)30㍑、
フォトギャラリー
この記事を見た人は次の記事も見ています
- 投稿者
- 本田 康之
- 日程
- 2025年05月16日 (金)~2025年05月16日 (金)
- メンバー
- イオンモール各務原店 本田
他1名
- 天候
- 晴れ
- コースタイム
- 第二駐車場(3分)受付所(11分)本堂登山参拝事務所(19分)文殊堂(3分)地蔵堂(2分)鐘楼堂(3分)観音堂(2分)投入堂(8分)文殊堂(20分)本堂登山参拝事務所(10分)受付所(3分)第二駐車場
- コース状況
- アプローチ
・車利用は国道179号から県道21号で三朝温泉経由で三徳山へ
・公共交通機関はJR倉吉駅から三徳山駐車場までバスがあります
①三徳山は受付所で入山志納金400円、投入堂受付で投入堂参拝登山料800円を納めます
②投入堂参拝受付時間は8時から15時(下山時間16時30分)、単独入山はできず、服装や靴のチェックが入ります。また配られる六根清浄のハッピ着用が必要です。
③前日に雨や当日に雨が降ると入山できませんので、ホームページで確認しましょう
⇒今回は昼から雨の可能性がありましたが、入山可能でした
④受付の先に門があり、下ったら、いきなりかずら坂と呼ばれる登りで、木の根道のような道が続きます
⑤最初に現れる文殊堂へ登る際に岩場の鎖場があります。ここは登りと下りで道が分かれています
⑥文殊堂が一番、高度感があり、お堂の木の板が細いです
⑦文殊堂からヤセ尾根のような細い岩の道が続きます。ここも登り下りで分かれます
⑧地蔵院は文殊堂に比べ。木の板が広く、文殊堂で慣れていれば、怖さはないです
⑨文殊堂の上で鐘楼堂があり、ここで鐘を1回つきます
⑩観音堂は岩場沿いを回り込む胎内くぐりがあります
⑪観音堂の先が奥の院でここが終点で、下から見上げる形になります
⑫下りは標識に従い、一部は専用道を歩きます。やはり文殊堂の下りがクサリ坂と呼ばれ、ここがポイントです。道は右左に分かれ、二人で同時に下れます。
⑬立ち寄り湯は三朝温泉に無料の河原風呂があります。旅館の一部でも1000円程度で日帰り対応しているところがあります。
- 難易度
-

感想コメント
三徳山と言った場合、投入堂(三徳山三佛寺)を指す場合が多いですが、この寺は中腹に過ぎないです。もちろん三徳山全体が境内になるわけですが、2015年には「三徳山・三朝温泉」が「日本遺産」の第一号として認定され、投入堂の名で知られる奥ノ院の建物は、中腹の断崖に浮かぶように建てられた他に類を見ない建築物で、国宝にも指定されています。断崖絶壁の上に建てられたお寺で、死亡事故が多発していることから、「日本一危険な国宝」という異名を持っています。
なお三徳山(みとくさん・899m)の山頂自体はもっと上の方にあり、この三佛寺からは登らず、南側から登ることになります。今回、昼から登るつもりでいましたが、雨が降りそうなので投入堂のみとしました。
8時からが受付開始で、8:30に通過するも先客がいるようです。登山靴で行きましたが、靴のチェックはソールになります。帰りにすれ違った方の靴を見るとスニーカーで登っている人もいて、今一つ基準がわかりません。
スタートからすぐに急な登りとなります。滑りそうな地面には土嚢袋の滑り止めが設置され、よく整備されていますが、木の根が地面に覆うような登山道でやはり登山靴が最適だと感じる所でした。
文殊堂まで来ると建物下より鎖場を登ります。ここは下りと登りが分かれていますので安心です。文殊堂は境内を一周するのですが、高台でさらに柵もなく、細いので高度感を感じることでしょう。ここで慣れると、上の地蔵堂の境内はちっとも怖くなくなります。
鐘楼堂で鐘を突いた後、細い岩場の通過辺りまでが危険個所のメインになります。
岩場の真下にある観音堂を過ぎると、もう終点の投入堂が現れます。写真でよく見る風景ですが、崖下にぱこっとはまったあの建物、どうやって造ったのか本当に不思議です。
投入堂はその直下で立ち入り禁止になっていますが、メンテナンスをするにしても命がけのように見えます。ここでいろんな角度で撮影を楽しみ、下山します。
帰りに文殊堂でもう1周してから下りましたが、結局3回ほど、回りました。
文殊堂の下りの鎖場は右左に分かれますが、右側の方が下りやすい感じがしました。ここは鎖を持てば、問題なしです。
下りはわりに早く下れました。
帰りは谷川天狗堂で栃餅を食べて、一服するとよいです。出来立てのような感じで柔らかくおいしいです。
本日の服装(春の低山)
①ウエアー
インナーは(アイスブレーカー)半袖Tシャツ
ボトムスは(マウンテンハードウェアー)3シーズンパンツ
②ギア
登山靴は(スポルティバ)「トランゴトレックGTX」、
ザックは(ブラックダイヤモンド)30㍑、