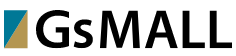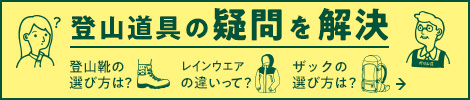巻機山の佳渓 ヌクビ沢支流三嵓沢右俣遡行(登川水系)
- 投稿者
-
伊藤 岳彦
横浜西口店
- 日程
- 2018年09月03日 (月)~
- メンバー
- 単独行
- 天候
- 晴
- コースタイム
- 桜坂駐車場(25分)割引沢渡渉点(60分)ヌクビ沢出合(30分)三嵓沢出合(30分)二俣(105分)井戸尾根登山道(80分)桜坂駐車場
- コース状況
- ※ 本文をご参照ください
- 難易度
-

感想コメント
三嵓沢右俣
越後の名山・巻機山の沢と言えば、米子こめこ沢がとても有名ですが、表参道と言える井戸尾根を挟んで、南西側には、割引われめき沢とその支流ヌクビ沢があります。
今回訪れたのは、ヌクビ沢のさらに支流となる三嵓みつくら沢。
ナメ滝と小滝の続く初級レベルの渓ですが、前半部で名のある美瀑を交えながら、変化に富んだ日帰り遡行を満喫することができます。
台風が近づく9月初旬、ちょっと詰めが大変でしたが、開豁な渓歩きを楽しんできました。
閑散とした桜坂駐車場を昼前に出発し、ぬかるんだ登山道で割引沢の渡渉点まで。
↑ 渡渉点
この先も沢沿いの登山道がありますが、昨今訪れる方はあまり多くはないでしょう。
渡渉点で沢装備を身に着け、本日も遡行開始。
上越らしい開豁な渓を目にすると、心が躍ります。
↑ 米子沢にも劣らぬ渓相です
連続するナメ床を越えていくと、大釜をもった2段8m滝へ。
↑ 2段8m滝
右岸登山道で容易に巻くことができます。
↑ 吹上ノ滝手前の淵
この淵は突っ込まず、右から簡単に越えられます。
↑ 吹上ノ滝10m
最初の名のある滝は、吹上ノ滝10m。
左岸に草付きスラブが明るく開けており、水流右を快適に登ることができます。
↑ 凹角の流れ
凹角の流れが25mほど続きますが、無理に突っ張る必要はありません。
途中登山道が沢を横切っていました。
↑ ここが登山道
この先で渓は右に曲がり、立派なアイガメの滝が現れます。
↑ アイガメの滝20m
この滝は2段滝。水流右から取り付きくと、大釜が現れます。
“アイガメ”というと我々は登山靴のパーツを連想してしまいますが、おそらく藍の甕かめを意味するのでしょう。
大釜を横切り、水流左に横断してから直上することで突破。
ここも右岸に明確な登山道があるので、巻きは容易です。
↑ これが藍甕あいがめなんですね
アイガメの滝を越えると、しばらくは平凡な渓相。
正面に迫力ある天狗岩を望むことができます。
↑ 天狗岩を望みながら
やがて二俣。左が割引沢、右がヌクビ沢です。
↑ 二俣
↑ 割引沢方面
↑ 分岐に案内あります
↑ ヌクビ沢に入ります
少し傾斜がキツくなりますが、特に難しいところはありません。
↑ 下山道あります
この巻道を使えば、入渓点まで50分ほどで戻ることができます。
やがて次なるハイライト、布干岩へ。
↑ 布干岩
布干岩は4段30m滝。ここで渓は左に大きく曲がります。
乾いた部分を選んで、容易に歩いていくことができます。
↑ この先は平凡な渓相
やがて三嵓沢出合へ。左岸より3段滝で合流します。
↑ 三嵓沢出合
また、ヌクビ沢本流には行者の滝15mがかかっています。
↑ 行者の滝15m
左岸巻き道が登山道にもなっています。
行者の滝を見物したら、三嵓沢へ入ることにします。
ここからは小滝とナメ滝を快適に登っていくことができます。
↑ 三嵓沢へ
↑ 5m滝
↑ 次の5m滝
↑ 続いて3m滝
この先二俣までは、ナメ状の滝とナメ床が続きます。
↑ ナメ床が続きます
↑ 7m滝?
やがて二俣へ。左俣は出合に5m滝をかけ、巻機小屋付近に突き上げるとのこと。
右俣はニセ巻機山直下の草原に出る、とあります。
↑ 二俣
↑ 左俣出合の5m滝
ここは登山体系で紹介されているように、右俣へ進むことにします。
↑ 右俣にかかる8m滝
↑ 上流部のナメ床
徐々に水線が細くなり、最奥の二俣へ。
右俣の垂直滝が登りにくそうなので、左俣へ入りました。
↑ 最奥の二俣は左へ
↑ 源頭部へ
↑ 登路を振り返ります
振り返ると越後の美しい山並みを望むことができます。
最後は露岩帯と草付きの斜面へ。
↑ 水が枯れて草と岩の世界へ
ここからはトラバース気味に井戸尾根を目指します。
↑ なだらかに見えて勾配きついです
とにかく上を目指せば、藪漕ぎはなさそうですが、草付きの滑りやすい斜面の直上も結構大変。
水平移動の方がまだ楽に思えたので、藪漕ぎ覚悟でトラバースを継続することにしました。
↑ 結局激ヤブ漕ぎになりました

↑ 赤線を辿りました
藪と格闘すること15分ほどで、突然登山道へ。
↑ ウオー!道だ!
ここからはのんびりと井戸尾根を辿り、桜坂駐車場へ戻ることができます。
マイナーな渓ですが、三嵓沢はとても明るく開放的。
日帰り遡行ルートとして米子沢ほど長くはないので、時間のない方やトレーニング遡行に最適だと思いました。
詰めをどうするかで印象が変わるような気がしますが、巻機山の美しい草付き斜面を彷徨い歩くのも面白いものです。
巻機山の神髄は北側(裏巻機)にあるように思いますが、今回は三嵓沢で巻機山の新たな魅力に触れ、その素晴らしさを再確認させられました。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。