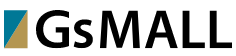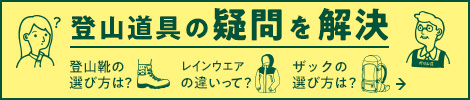奥秩父山塊 主脈 全山 縦走
- 投稿者
- 田渕 幹敏
- 日程
- 2012年08月29日 (水)~2012年09月03日 (月)
- メンバー
- ららぽーと横浜店 田渕 (TL)
他 3名 (内1名は3日目に下山)
- 天候
- 08/29 晴 ⇒ 08/30 晴 ⇒ 08/31 晴のち小雨 ⇒ 09/01 雨 ⇒ 09/02 雨 ⇒ 09/03 霧
- コースタイム
- 【08/29】
瑞牆山荘 ⇒ (6:10) ⇒ 大弛小屋 (テント 泊)
【08/30】
停滞 … 北奥千丈岳 ピストン (テント 泊)
【08/31】
大弛小屋 ⇒ (7:40) ⇒ 破風山避難小屋 (避難小屋 泊)
【09/01】
破風山避難小屋 ⇒ (9:40) ⇒ 将監小屋 (営業小屋 泊)
【09/02】
将監小屋 ⇒ (9:05) ⇒ 鷹巣山避難小屋 (避難小屋 泊)
【09/03】
鷹巣山避難小屋 ⇒ (4:25) ⇒ 奥多摩駅
※ 休憩を含まない時間です。
- コース状況
- ロングトレイルの常ではあるが、人が多く入っている部分とそうでない部分の差がとても大きい。
知名度の高い登山道はきちんと整備されておりトレースも良くついているが、人の入らない地域はあまり手が入っていない。
そう言ったヶ所はトレースも薄く道標も少ない為、道迷いに注意が必要。
最低限の読図能力は必須になる。
人入りの少ないヶ所で特に顕著だが全体として巻道が歩き難い事が多く、場合に因っては稜線通しよりも巻道の方が時間がかかったり道迷いのリスクが高い場合がある。
これは、稜線より山腹の方が道が見付け辛い事/暗い場合が多い事/細く整備されていないトラバース道では平坦であっても思いの外時間を要する場合がある事/巻道は昭文社の「山と高原地図」の時間設定が厳しい事・・・、等が理由に考えられる。
もちろん"強風/雷/降雨雪"などの場合は迷わず巻道を選ぶべきだが、上記を考慮して時間設定には余裕を見る事が必要になる。
八ヶ岳や北アルプス等の人気山域に比べると営業小屋の密度が薄い。
必然的にテントもしくは避難小屋利用が前提となる上、予約時のみや週末のみの営業としている小屋も多く有事の際の支援も受け辛い。
余分な水や食料などを含めたある程度の重量を背負って、長時間行動が出来る体力が必要になる。
- 難易度
-

感想コメント
僕の登山は筑波山をホームにスタートしました。
幼少の頃から何度も登り、家から自転車で登山口まで行き山頂を越えたりもしています。
初めて遭難したのもこの山で(笑)、登山者としての僕の原点を育んでくれた親の様な山だと思っています。
登山に仕事として関わる様になってから一番登っている山はと言えば、谷川岳と西穂高岳でしょうか。
電車でアクセス出来て日帰りも可能、冬期は降積雪があり四季を通して厳しいアルピニズムも学ばせてくれる。
癒しや楽しみを与えてくれると同時に大きな壁となって立ちはだかりチャレンジの場も与えてくれる、良き友人の様な山と言えるかもしれません。
そして奥秩父の山々…、秩父の山は僕にとっては先生です。
初めての単独行も初めてのテント泊も秩父でしたし、主催する登山チームの初山行も秩父へ行きました。
ソロで初めて登った時の不安感…、遥か遠く微かに響く遠雷が怖くて泣きそうになっていたのを思い出します。
初めてのテント泊が単独行だった僕は、誰もいない晩秋の白岩山に独り幕営し夜のあまりの暗さと街の灯の美しさにドキドキしていました。
休みが取れると池袋のマンションを深夜や早朝に出発し、西武池袋線に乗り込んで秩父を目指す!
山岳部や山岳会に入らず独学で登山を学んだ僕にとって、いつだって先生は「山と渓谷社の本」と「秩父の山々」でした。
奥秩父山塊は、東アルプスと称される事もある深く美しい山域。
田部 重治は、1919年刊行の「日本アルプスと秩父巡礼」に於いて"水が豊富で豊な森林と、渓谷美が素晴しい"とこの山域を讃えました。
それから90年以上経った今、奥秩父山塊にはもう1つ大きな魅力が生まれています。
山域の登山を支える山小屋の人々の暖かさです。
立ち寄った全ての山荘が雨に濡れた僕らを直ぐにストーブに火を入れて迎えてくれ、時に温かい珈琲まで戴いたりもしました。
「秩父は八ッや北アみたいに人が来ないから、小屋番も人恋しいんだよ。」と照れ隠しを言いながら、(テントと避難小屋を繋いで旅をしたので)泊まりもしない僕らにどこまでも親切でした。
山を愛し山を歩く人を愛する秩父の山荘の在り様は、山小屋の原点でもあり未来への指導標でもあるのではと感じています。
今回歩いたトレイルは、個々の登山の難易度は高くはありませんがロングトレイルであるが故の難しさがあります。
気象判断/読図能力/タイム管理/体調管理/歩行技術/生活技術/有害な動植物への対応/体力と精神力/有事の際の対応力、…等々の総合力が必要になるからです。
「長期になる」と言う事は、それだけで山行の難易度を大きく上げるのです。
でも、ある程度の期間を山の中で過ごし山域を通して歩く事で見えてくる事もまた沢山あります。
それは中々巧く言葉に出来るものでは無いのですが…。
長い縦走の時に自分が感じている漠然とした喜びを、正確ではないながら言葉にしようと努力するならそれは以下の様な想いかもしれません。
- クライミングも登山も普段僕らは自然と文明の境界線で遊んでいる。
- でも深く山に入り長期縦走やバリエーション登山をする時、その境界線を少しだけ越えて山の側に入って行けた気がする。
- その事の恐怖や興奮や癒しをより強く深く鮮明に感じる。
- そして、山が…自然が…少し身近になり少し深く繋がれたと感じるのだ。
仲の良い友と苔むした美しい山々を歩いて動物達や人の暖かさに出会う、そんな旅が出来てとても幸せでした。
お風呂に入りたくて堪らないのにそれでもやっぱりまだ山を降りたくない自分に気が付いて、何故だか嬉しい気持ちになりました。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。