南八ヶ岳~根石岳 紅葉テント泊縦走 1日目
- 投稿者
-
日下部 友哉
さいか屋横須賀店
- 日程
- 2020年10月12日 (月)~2020年10月13日 (火)
- メンバー
- 他1人
- 天候
- 晴れ
- コースタイム
- ・1日目 行動時間:7時間40分+休憩
天女山(15)天ノ河原(120)前三ツ頭(35)三ツ頭(45)権現岳(80)キレット小屋(100)赤岳(30)地蔵の頭(35)行者小屋
※()内単位:分
累積獲得標高:1833m
歩行距離:10.08km
- コース状況
- ・権現岳長い梯子あり。気を緩めないように。
・キレット小屋手前は足場狭い、鎖あり。
・キレット小屋から赤岳山頂までは長い岩場、ガレ場、鎖場、梯子あり。落石させないよう歩きましょう。ヘルメット推奨。
・地蔵尾根の上部は鎖場、梯子あり。
◾️山小屋・テント場
行者小屋 テント泊予約不要。受付、売店は赤岳鉱泉へ。行者小屋テント場は水場、トイレは利用可能。
※権現小屋、キレット小屋、赤岳頂上山荘は営業していません。
◾️気温
キレット小屋 11:50 20℃
行者小屋テント場 17:30 12℃
◾️アクセス
マイカー:天女山駐車場 天女山展望台近くにトイレ有り
バスと電車、タクシーを利用して車回収。
・小海町町営路線バス:稲子湯13:56→松原湖駅入口14:28 ¥600現金のみ
・JR小海線:松原湖駅14:55→甲斐大泉駅15:47 ¥680現金のみ
・タクシー:甲斐大泉駅から天女山駐車場 ¥1640
- 難易度
-

感想コメント
八ヶ岳南部紅葉テント泊縦走。
本当は安達太良山に行きたかったのですが、福島方面の天気が悪く、長野県中部の天気が良さそうだったので久々の八ヶ岳へ。なかなか稜線ルート上にテント場がなく、1回稜線を外れないといけないので面倒くさがってあまり八ヶ岳でテント泊してませんでしたが、今更ながら車を入山口に置いてバス・電車を使って車を回収すれば意外と縦走が楽しめるではないかと気付いた訳です(笑)
◾️1日目
天女山から権現岳、キレット、赤岳と縦走して、行者小屋でテント泊。天女山駐車場に車を置いて出発です。何年も前に冬の天候悪い時に来た権現岳。無雪期は初めてです(笑)冬の記憶を思い出しながら登ります。熊笹に囲まれた急な辛い登りを登り詰め前三ツ頭に到着。道中はガスってましたが晴れてきて、南アルプスが見えてきました!次は三ツ頭へ。まだまだ登りですが編笠山と岩の中に青い屋根の青年小屋が見えてきて三ツ頭に到着。西側は雲海がすごいです♫そして権現岳へ。一部岩場をトラバースして山頂へ。ギボシもなかなか存在感ありますね。
いよいよ赤岳への縦走路で有名な長い梯子。これ本当に長い梯子で、まだ終わらない?ってくらい長いです…そして足かけるところも細い。なかなかに緊張感あります。しばらく進むと景色が開けるとこに出て、今まで見えていなかった阿弥陀岳と赤岳が雲の中からじわじわと…来た!やっと見たかった景色が、なかなかの迫力です!昨冬歩いた阿弥陀南稜もクッキリと見えてきました♫なかなか登り詰めますね。どこを歩くのか?(笑)そしてやっとキレット小屋が見えてきて到着。小休止。日差しが強く暑いくらい。小天狗、大天狗がとてもかっこ良い。
ルンゼ手前でストックをしまい、ヘルメット着用。いよいよ岩場登りです。ガレているのと岩が結構脆いので注意しながら登ります。結構キツイ登りです。相方の山コーディネイトがモノトーンなので写真映えしない、岩場にカモフラージュしている(笑)。谷筋の紅葉が綺麗です♪だんだんと標高が上がってくると風が出てきましたが日差しがあるので丁度良い気候に。稜線に出ましたが赤岳までは以外と遠い。梯子や鎖場もあるのでまだまだ気は抜けません。文三郎尾根の合流地点まで来ればあと少し。ようやく赤岳に到着しました!風が強くさすがにちょっと休憩していると寒いのでウィンドシェルを羽織りました。雲が勢いよく流れます。
赤岳天望荘で休憩がてら軽食を頂こうと下ります。バターチキンカレーを頂きました。小屋内は風もなく暖かい日差しが入り眠くなります(笑)。時間も良い頃なので再出発。地蔵尾根で行者小屋へ下ります。この道もそういえば今まで冬しか歩いたことなかったです(笑)無雪期も岩場、階段で歩き辛いですね。森林限界以下になって苔が増えてきてようやく行者小屋に到着。
そこそこにテント泊者がいました。水場もトイレもテント場からすぐ近く。樹林帯なので風の影響を受けづらいのは寒くなってくると助かりますね。夕飯は栗ごはんと豆乳鍋を♪稜線はガスってしまい、下からは見えなくなってしまいました。ダウンジャケット&パンツを着て、翌日は早い出発なので早めに就寝。
2日目に続く。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。

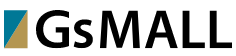













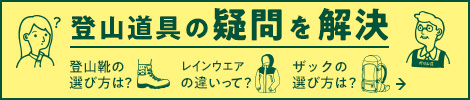


 (640x480).jpg)




