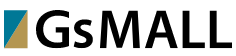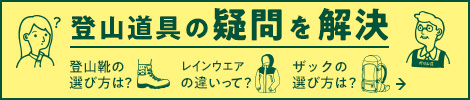奥秩父 金山沢大荒川谷遡行 ~ 紅葉の美渓に孤影を曳く珠玉の沢旅 (破風山北東面 入川支流)
- 投稿者
-
伊藤 岳彦
横浜西口店
- 日程
- 2015年10月14日 (水)~2015年10月15日 (木)
- メンバー
- 単独行
- 天候
- 晴時々曇
- コースタイム
- ■ 10月14日(水)
入川渓流観光釣場(60分)赤沢谷出合(150分)柳避難小屋
■ 10月15日(木)
柳避難小屋(60分)金山沢出合(110分)ゴンザの滝(60分)小荒川谷出合(90分)中ノ二俣(50分)三俣(80分) 稜線登山道(40分)雁坂峠(180分)入川渓流観光釣場
- コース状況
- ■ 入川渓流観光釣場 駐車料金¥500/日
■ 登山道から金山沢出合への下降点は道標が目印
■ 下降路は急峻なれど踏み跡明瞭 赤テープ多数
■ 金山沢出合には古い標識あり
■ ゴンザの滝は左岸巻き踏み跡辿る ルンゼの下降も容易
■ ゴルジュは右岸巻き 下降点にかなり古い残置スリング
■ 小荒川谷出合先に幕営適地
■ 大荒川谷の滝は落差あるもほとんど直登可能
■ 中流部の一部 倒木で荒れた渓相
■ 三俣から左俣に入るも倒木が谷を塞いでいます
■ 三俣からは早めに枝尾根に取り付き稜線へ
- 難易度
-

感想コメント
Ⅰ.概要
秩父盆地から関東平野を辿り、東京湾に注ぐ大河川・荒川。
その水源は奥秩父北面に源を発する「大血川」「中津川」「大洞川」「滝川」「入川」、これら5つの谷に分かれます。なかでも「入川」は荒川水系最奥の源流であり、川又で「滝川」を分けた後、さらに矢竹沢・赤沢谷・中小屋沢・金山沢・松葉沢・股ノ沢を分け、本流である真ノ沢が名瀑・千丈ノ滝を懐に抱き甲武信ヶ岳に突き上げています。
今回のルート「金山沢」は、柳避難小屋の下流1kmのところで右岸より入川本流に注ぐ大変水量豊富な渓。
美瀑・ゴンザの滝を擁し、多くの釜と深いゴルジュを越え、途中「小荒川谷」を分けて「大荒川谷」と名前を変えると、直登可能な美瀑とナメ滝を巡る世界となります。
渓の美しさは通好みではありますが、奥秩父最強!?と謳われることもあるほど。
真ノ沢や股ノ沢に勝るとも劣らない深山幽谷の渓相のなかで、清流と美瀑が煌めき、原生林と苔の美しさが際立つ自然の芸術美は、まさに奥秩父の真髄!と言っても過言ではありません。
この渓を遡行する場合、通常は沢中1泊2日で行われます。
パーティー遡行であれば、車1台を「出会いの丘」にデポし、別の車1台で入川渓流観光釣場に移動するのが一般的。中には自転車1台をデポするパーティーもあると聞きます。こうすれば、雁坂峠から黒岩尾根を辿って下山することが可能となります。あるいは、雁坂トンネル料金所ゲート脇無料駐車場に車1台を置き、雁坂峠より山梨県側へ最短で下山することもできるでしょう。
金山沢出合までは、柳避難小屋へと続く登山道の途中から枝尾根を下降するのが時間的にもっとも早いルートですが、赤沢谷出合から入渓し、入川本流を遡行することも可能です。しかし後者は結構体力を消耗するので、盛夏のベテラン向けといったところでしょうか。また泊地としては、小荒川谷出合先に絶好のビバーク適地があるので、ここを利用するケースが多いようです。
しかし、今回は(今回も!?)独りの沢旅なので、入川観光渓流釣場に車を停めて、周回してくるより方法がありません。もちろん沢中1泊2日がベストですが、初日は柳避難小屋泊でゆっくりし、2日目に本気モードで遡行することにします。軽量化を言い訳に、たまには奥秩父の山小屋泊を愉しみたいという誘惑を抑えることができませんでした。と、このような感じで荒川水系随一の美渓として誉れ高い「金山沢大荒川谷」へ、今回満を持して訪れてみました。
Ⅱ.金山沢大荒川谷遡行
1.柳避難小屋へ
そろそろ秋が深まり山々も色付き始めた10月の平日、心潤す沢旅を求めて再び荒川源流域へ。
深夜の国道140号を走らせた後、最近は「道の駅みとみ」でもなく「出会いの丘」でもなく、真っ暗で寝やすい「広瀬ダム駐車場」で爆睡するのが常となっています。翌朝11月末まで通行無料の雁坂トンネルを越え、埼玉県側へ。入川渓流観光釣場に車を停めて出発したのが、昼前というスロースタート。赤沢谷出合までは左に入川の豊かな流れを愛でながら森林軌道跡を辿ります。赤沢谷出合はベンチもあり、休憩に適した場所です。
7月の末に一度ここを訪れ、その時はここから入川本流を遡行しましたが、豊富な水量と低水温、そして勢いある水流に難儀し、赤沢谷出合から柳避難小屋まで5時間以上かかってしまいました。
決して際立った大滝やゴルジュがあるわけではありませんが、ツルツルであと一歩が越えられない小滝や、中途半端に厄介なゴルジュがあり、大高巻きや懸垂下降を強いられ、疲労困憊となった苦い記憶だけが残っています。しかし今回は水温の低さを嫌って、柳避難小屋まで“素直に”登山道を辿ります。
道は赤沢谷出合から少し上にある赤沢吊橋を渡った後、徐々に傾斜を増し、山腹の長いトラバースとなっていきます。古くは昔の地形図に書かれていたように入川本流沿いに渓谷道があったようですが、今は完全な廃道。しかしその後開かれた山腹のトラバース道は釣師御用達なのでしょう、道は崩壊もなく明瞭で赤テープも豊富にあります。
赤沢谷出合からさらに3時間弱で、今宵の泊地である柳避難小屋へ。初日は単なるトレッキングでしたが、紅葉に陽が差し込むなか、秋めく静かな森を十分に堪能することができました。
柳避難小屋はまるで別荘のような、とてもきれいなロッジ風の山小屋です。
十畳一間くらいの小屋ですが、きれいに清掃され、多くの方に愛用されているのが分かります。小さなちゃぶ台にまな板まで置いてありました。
本物の釣師か沢ヤしか訪れることがないような小屋で、なかなか登山者には馴染みのないルート上にありますが、奥秩父の山小屋の良さを味わえる素晴らしいロケ―ションは、まさに知る人ぞ知る穴場的な存在でしょう。
こんなにも喧騒と無縁で、豊富な清流が横たわる山小屋はそうあるものではありません。私の記憶にある限り、この柳避難小屋に匹敵するのは、南アルプスの大門沢冬期小屋くらいかもしれません。
釣師の方が多く訪れると聞きますが、さすがに10月平日なので、この日は私一人。
絶え間ない豊かな瀬音に包まれながら、自分の時間を満喫することができました。
2.金山沢出合へ
翌朝は明るくなってから入渓点を目指します。
昨日辿ったトラバース道を戻り、少し登り返してしばらく枝沢を幾つか渡ると、金山沢への下降点へ。「金山沢出合は→」という道標があるわけではありませんが、【←十文字峠/川又→】とある朽ちた道標がある場所が目印です。晴れていれば樹木越しに、金山沢が入川本流を挟んで遠望できるでしょう。
下降路はやや急峻ですが、踏み跡は明瞭。赤テープを頼りにグングンと高度を下げます。よくある下降路のように残置ロープなどはありませんが、地形の弱点を突いた見事なルート取りに感心してしまいました。
3.美瀑・ゴンザの滝
15分くらい下るといよいよ金山沢出合へ。
紅葉のピークはまだまだ先のようですが、奥深い渓を辿る緊張感で身の引き締まる思いがします。
金山沢は10月とはいえやはり水量が豊富な渓。ヒリヒリと痛いくらい冷たい水に腰まで浸かるのは我ながらドMな行為ですが、秋の遡行とはこのようなもの。体力を無駄に消耗しないようにしながら、穏やかながら長い渓を黙々と突き進みます。
金山沢のハイライトは、美瀑・ゴンザの滝と、その先に続く顕著なゴルジュ帯。
迫力あるゴンザの滝は下から見える2段と、続く上に2mと5mがある計4段の滝。直登不可なので、通常左岸を巻きます。何となく踏み跡があり、下降路もルンゼにつけられています。ここも地形の弱点をよく突いていたものでした。
↑ ■ ゴンザの滝 ■ ↑
ゴルジュ帯には4m滝があり、盛夏ならシャワーで突破できるようですが、ここもセオリー通り右岸を巻きます。下降地点は急峻なルンゼ状ですが、かなり古い残置スリングがあるものの、ロープなしで降りられました。
入渓から3時間弱で小荒川谷出合へ。
小荒川谷はかつては大荒川谷以上にナメ床の続く美渓でしたが、東側の大崩落によって釜が埋まり、遡行価値を失ってしまったとても残念な渓。紅葉をバックに、勢いよく水が流れ込む渓の姿が印象的でした。
出合の先には右岸左岸ともに幕営適地があり、薪木も豊富。次回訪れるときは是非ここで一夜の夢を預けたいところです。
4.大荒川谷へ
大荒川谷に入っても水量は衰えず、苔むした渓相と紅葉がマッチしながら渓は佳境へ入っていきます。
ここから先は名前のある滝はないものの、美瀑とナメ床が交互に現れ、その美しさに触れるたびに水の中に足が止まります。滝は落差があるものの、直登可能なものが多く、快適に登っていくことができます。
しかし、この辺りまで来ると集中力の欠如がみられ、細かい足の置き場が雑になっていきます。つくづく沢登りは体力勝負であることが改めて思い知らされます。
幾つもある滝をどのように登ったかも思い出せないほど無心でひたすら渓を歩き続けること5時間。ようやく上流部の三俣へ。
水量が依然豊富なのが中俣で、右俣は涸沢。一般的には左俣を辿りますが、台風などの影響かかなり山は荒れ、左俣には倒木が多く見られます。どのみち渓は伏流し、涸れてしまうようなので、思い切って三俣で遡行を終了し、枝尾根に上がることにします。最初こそ脆いガレ沢を強引に登り詰めましたが、枝尾根に上がってしまうと傾斜は地形図通り緩く、しかしヤブではありません。何となくある獣道を辿るように進みますが、意外にも快適に距離をかせぐことができます。この辺りは手つかずの自然が広がるとても美しいところ。緑のフカフカとした苔や倒木、威厳さえ感じられる原生林のなかを土足で歩くのは何だか申し訳ないとさえ思ってしまいました。
遡行を終えたあとの詰めは辛いもの以外の何物でもないと思っていましたが、大荒川谷の詰めでは本当に素晴らしい森の彷徨を堪能することができました。
5.稜線へ
遡行終了から80分ほどで、ようやく奥秩父主脈登山道へ。
いつもそうですが、目の前に登山道が現れたときの感動!?は、何とも形容しがたいもの。「生還した!(=これで無事に帰れるだろう)」という安堵の感情と、「やっぱりオレってすごいかも!(=念願の渓を独力で突破した)」という稚拙なナルシズムが心の中でゴチャゴチャになり、ものすごいハイテンションになってしまいます。ここからは先、あとはサクサクと登山道を歩くのみ。
因みにコアな下山ルートとして、破風山の北側に伸びる尾根上にかつて存在した破風山歩道(破不山歩道とも)を使うという手もあります。スズタケの猛烈藪漕ぎ必至の完全廃道ですが、北を目指してガンガン降ればいずれは真ノ沢林道(これもほぼ廃道ですが...)にぶつかり、何とか柳避難小屋に戻ることができ、そうすれば柳避難小屋をベースとした周遊ルートも可能になるでしょう。
しかしこれはまた次の機会ということにして、今回は“素直に”登山道を東へ。
雁坂峠の南斜面はとても開けていて、いつ来ても何度訪れても、気持ちを爽快なものにしてくれます。さすがは日本三大峠に恥じない景観です。
6.突出尾根
雁坂峠から川又までは突出尾根--雁坂嶺より北東に派生する尾根を辿ります。
この道は日本で一番古い歴史をもつ峠越えの道で、甲州と武州を結ぶ重要な交通路。
戦国時代には、武田信玄公が雁坂峠に狼煙場を設け、軍事用道路としただけでなく、甲斐府中の鬼門であるがために罪人放逐の道にもされ、さらには武田家滅亡の際に残党の逃避行ルートとしても使われたようです。
その後信仰の道として、善光寺詣、身延山久遠寺詣、冨士山信仰などの道として多くの人々に利用されただけでなく、日本のシルクロードとして秩父大滝村の人が繭を塩山の繭取引所へ運ぶ道としても利用されたようです。
こんなにも歴史の重みを感じながら、美しい原生林のなかを歩くことができる峠道は他にはないでしょう。
7.孫四郎峠
雁坂小屋より約30分。地蔵岩分岐の手前にある小さな鞍部に孫四郎峠があります。
現在の登山道は峠の東側を巻いているようなので、わざわざ立ち寄る方はいないかもしれません。昭文社エアリアマップには名前の記載もない峠ですが、ここからかつて荒川小屋のあった小荒川谷出合まで道が通じていたと言われます(後述)。ちなみにこの峠の名の由来は、その昔旅人の荷物を雁坂峠まで運んで、その駄賃で暮らしていた孫四郎という人物によるもの。雁坂峠までは長くて険しく、荒川小屋の分岐まで来ると、背負っていた客の荷物をおろし、お客さん、ここが雁坂峠だよ、と偽って駄賃をもらうと、さっさと引き返してしまったそう。いつしか村人たちはその峠を孫四郎峠と呼ぶようになったと言われます。
8.黄昏の渓を振り返る
孫四郎峠を巻き、さらに北へ進むとやがて地蔵岩の分岐へ。
そろそろ日没が迫ってきていますが、この日遡行した大荒川谷のみならず、入川水系すべてを眼下に見下ろせるスポットへ立ち寄ります。苦労した遡行のあと心地よい充実感を胸に、自分が辿った渓を感慨深く見つめるひと時ほど心に深く残るものはありません。黄昏の地蔵岩に佇みながら、赤い夕陽のもと眼下に黒い谷を見下ろし、今日一日辿った渓のさまざまな貌を思い出しました。
金山沢大荒川谷はシンボリックなスポットが少ない分、決してインパクトのある渓ではありません。渓を比較するのはナンセンスかもしれませんが、同じ荒川水系の他の渓と比べても、豆焼大滝や両門の滝を擁する「豆焼沢」の方が印象に残る気がしますし、ナメ床の広がる苔むした渓相は「古礼沢」の方が上かもしれません。
しかし言葉では上手く表現できない渓としての奥深さはやはり荒川水系屈指のもののような気がします。きっと一度くらいの遡行で、金山沢大荒川谷の素晴らしさは理解できないのでしょう。もっと経験を積んで、違った角度から渓を見ることができるようになったときに再訪し、この渓について自分の言葉で語ることができるようになりたいと思います。
Ⅲ.荒川林道について
奥秩父の魅力に憑りつかれると、その歴史を紐解いてみたくなるものです。
歴史の豊饒さにおいて、奥秩父に勝る山域はないというのは言いすぎでしょうか。
一例として、古くからある人の営み、その生活の痕跡を「失われた道(廃道)」に見ることができるのも奥秩父の隠された魅力の一つです。
今回訪れた金山沢大荒川谷に関連したものでは、まず「旧荒川林道」の存在が浮かび上がります。
かつては入川林道の対岸に「荒川林道」があり、入川橋から突出尾根の北面をトラバースするように小荒川谷出合にある荒川小屋まで道が通じていたとされます。
木暮理太郎、田部重治に続いて1925年頃から奥秩父に分け入り、先人と同じように奥秩父を自己の山たらしめた原全教(1900-1981)。その空前絶後の名著『奥秩父 続』(昭和十年七月朋文社刊)によると、“入川橋の上袂から上る雁坂道から分かれ辿ること胴木小屋沢へ二時間半を要し、胴木小屋沢から金山沢の二俣、荒川小屋まで約二時間”と書かれているそうです。
そして荒川小屋からは、柳避難小屋へ下る裏股ノ沢林道(沢のエスケープにもなる)と、前述した孫四郎峠に通じる道があり、おそらく林業従事者が利用していたと思われます。
奥秩父の山小屋の多くはもともと登山者の利便を図るために造られたものではないそうです。
甲武信小屋、大弛小屋、柳避難小屋、樺避難小屋、滝川の釣橋小屋が営林目的に造られたのと同じように、荒川小屋もきっとその目的で利用されていたのでしょう。
ちなみに、将監小屋、笠取小屋、雁坂小屋などは水道水源林の管理のために生まれた小屋であるそうです。
私のような物好きな!?沢ヤしか訪れない小荒川谷出合に「荒川小屋」というものがあって、仕事をしていた人がいたなんて、今ではとても信じられない話です。
Ⅳ.妙法鉱山について
さらにもう一つ信じられないのが、小荒川谷出合にあったという「妙法鉱山」の話。
「金山沢」という名前はそこに鉱山があったことを一般に示すとされ、歴史に埋没してしまった痕跡を知る手がかりを与えてくれます。
ちなみに奥秩父には入川の金山沢のほかに4つの金山沢ーーー笛吹川東沢の金山沢、滝川の金山沢、本谷川(金峰山西面)の金山沢本谷、中津川神流(かんな)川の金山沢がありますが、奥秩父に金山沢と称される沢が特に多いのは、かつて武田信玄公が鉱山開発に力を注いでいたという史実と無縁ではないのでしょう。
しかしこの妙法鉱山は、いわゆる怪しい埋蔵金伝説!?などとは別に、昭和初期に実在した鉱山。荒川小屋から20分ほど登ったところに坑道があり、金や銅、磁鉄鉱が採れるかなり有望な鉱山で、太平洋戦争中は軍の資金により、試掘が行われていたそうですが、終戦後の大嵐によって何もかも流されて閉山になったようです。往時は多くの人が物資の搬入搬出のために訪れ、孫四郎峠を経て山梨側への往来が盛んであったとされます。
昔は生活するために当たり前のように人が訪れていた場所が、今では泊まりの沢装備がないと行けない場所になってしまっていることが何だかとても不思議な感じがします。
自分の沢旅を有意義なものにするために今回はあらかじめこのような歴史を調べてから訪れましたが、特に小荒川谷出合に立ったときは、まさに古人の息遣いを感じたような錯覚を覚え、まるでタイムスリップしたかのような気分に陥りました。
山の中を歩く(=渓を遡る)というのは本当に奥の深い行為です。
目的地を目指してひたすら歩く、あるいは花や景色を愛でながら楽しく歩く、人が山を歩く理由は十人十色ですが、歴史に思いを馳せることをほんの少し心に付け加えてみると、その山行の意義がより深くなるような気がします。歴史を通じ古人の生き方について考えてみることは、自分が行っている登山とは一体何であるか、何故渓を遡るのか、そして最後には自分が何者であるのかという哲学的な思索に昇華されていきます。
Ⅴ.終わりに
山を知るということは、単にピークを踏んで終わりということではないはず。
その山に開かれた道を全て辿り、分水嶺としての渓を遡り、四季を通じて移り変わる様々な山の貌を知り、そしてその山に関わってきた人々の歴史の痕跡を感じることであるように思えます。
まだまだ奥秩父には私の知らない世界が無限に広がっています。
ただ単に遡行するだけでなく、そこに隠された歴史に思いを馳せることを大事にしながら、これからもまだ知らぬ渓を彷徨ってみたいと思います。
きっとその遡行は私にとって新たな思索の旅になっていくことでしょう。
【参考資料】「奥秩父 山、谷、峠そして人」 山田哲哉さん著 (東京新聞社)
サイト「山里の記憶151」 雁坂トンネル公式サイト など
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。