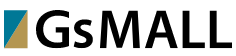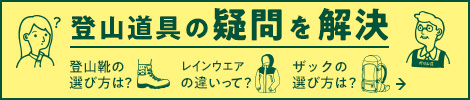西丹沢 癒しの渓 モロクボ沢 (畦ヶ丸北東面白石沢支流)
- 投稿者
-
伊藤 岳彦
横浜西口店
- 日程
- 2016年07月29日 (金)~
- メンバー
- 単独行
- 天候
- 曇
- コースタイム
- 西丹沢自然教室(20分)用木沢出合ゲート(40分)入渓点(15分)モロクボ大滝下(45分)石積み堰堤(10分)水晶沢出合(40分)越場ノ沢出合(30分)善六ノタワ(60分)西丹沢自然教室
- コース状況
- 本文をご参照ください
- 難易度
-

感想コメント
モロクボ大滝
首都圏では貴重なウォーターワールド、モロクボ沢。
茹だるような都会の暑さから逃れたいとき、訪れたくなる癒しの渓の代表格です。
梅雨も明け、猛暑が迫る7月の終り、大滝と釜を巡りながら、心と体をリフレッシュしてきました。
2016/7/29 曇
西丹沢自然教室[11:49]…用木沢出合ゲート[12:08]…入渓点[12:48]…モロクボ大滝下[13:00]…石積み堰堤[13:45]…水晶沢出合[13:56]…越場ノ沢出合[14:42]…善六ノタワ[15:09]…本棚見物[15:37]…下棚見物[15:50]…西丹沢自然教室[16:15]
目次
中川川流域を訪れるときは、西丹沢自然教室前の駐車場で仮眠するのが定番。
疲れ切っているのか、この日は昼近くまで爆睡してしまいました。
モロクボ沢を遡行するときは、用木沢出合にあるゲート前まで車を進めることもできますが、混雑も予想されるので、今回は入渓までのウォーミングアップをかねて、西丹沢自然教室前から歩くことにしました。
↑ 西丹沢自然教室前より西沢出合を望む
白石沢沿いの林道は広々とした気持ちのよい空間。
賑わうキャンプ場を横目に、用木沢出合にあるゲートまで20分ほど。
↑ 用木沢出合にあるゲート
その先をしばらく進むと、白石沢に架かる幅1.5mの古いコンクリートの橋が見えてきます。
ここがモロクボ沢の入口です。
↑ 左の橋を渡ります
橋を渡ると白石沢キャンプ場跡地。左手に下り、その先の道をさらに進みます。
↑ まだ舗装路が続きます
↑ 赤い山彦橋を渡り、さらに奥へ
この辺りはどこからでも入渓できますが、堰堤がまだ数基現れるので、枯れ沢であるショチクボ沢出合で沢支度を整え、入渓することにします。
↑ 入渓点
最後の堰堤を右から巻き、苔むした穏やかな渓相のなかをゆっくりと進みます。
↑ 何やら大きな瀑音が......
↑ モロクボ大滝が見えてきました
【↓】 モロクボ大滝
モロクボ大滝30mはマイナスイオン全開の美瀑。
この日はやや水量少なめなのか、迫力に欠ける感がありましたが、やはりいつ見ても美しい滝です。
大迫力大水量の大滝を求めて、あえて大雨の翌日などに訪れるのもよいかもしれません。
大滝を越えるには、右岸の高巻きがセオリー。
直登は人工登攀となってしまいますが、巻き道は明瞭なので、容易に上に抜けることができます。
↑ 高巻きは滝の左から
↑ チムニー状の隙間を腕力で乗り越えます
↑ その先は右にトラバース
↑ 容易に落ち口へ抜けられます
【↓】 美しい滝と釜の饗宴
大滝を越えると、大きく深い釜をもった連瀑帯が石積み堰堤まで続き、この辺りが一番心癒されるところと言われます。
時間の許す限り、エメラルドグリーンの釜で水と戯れ、心をリフレッシュしたいところです。
↑ 石積み堰堤で核心は終わりとなります
↑ 右から容易に越えられます
↑ 堰堤上から見下ろす
【↓】 後半部と詰め
石積み堰堤を越えると、後はやや冗長な苔むしたゴーロ歩きとなります。
午後の優しい陽射しを浴びながら、ゆっくりと歩を進めていくと、やがてジャンクションである水晶沢出合へ。
↑ 水晶沢出合へ
水晶沢出合で本流は左へ大きく曲がります。
下ばかり見てると、知らず知らずのうちに水晶沢へ入ってしまうので、ここは注意したいところです。
↑ 水晶沢方面の様子
↑ 今回は本流へ進みます
本流はこの先いくつかのナメ床が迎えてくれますが、残念ながら平凡な渓相となり、特に見所はありません。
水晶沢出合から先の詰めは様々なルートを選ぶことができますが、今回は疲れを残さないために、本流右岸の枝沢である越場ノ沢を詰め善六ノタワへ抜けるルートを選択。
おそらくこれが最短で下山できるルートになるでしょう。
ただ越場ノ沢出合に目印がある訳ではないので、地形図が頼りです。
右岸に比較的広く大きい、傾斜のゆるい枝沢が見えてきたら、それが越場ノ沢。
水晶沢出合より30分ほどです。
↑ 越場ノ沢に入ります
↑ 徐々に傾斜がきつくなっていきます
越場ノ沢は水流のほとんどない枯れ沢。
右にカーブしながら忠実に沢型を辿ると、登山道のある尾根が見えてきます。
↑ 沢型を忠実に詰めます
適当なところで、立ち木のモンキークライムで強引に斜面を攀じ登ると、登山道はすぐそこです。
↑ もうすぐ登山道です
↑ 登山道に出ました
上手に詰め上がれば、善六ノタワより少し西の地点に出ます。
あとは一般登山道を駆け下るのみ。
途中少し寄り道をして“本棚”と“下棚”という丹沢を代表する大滝を見ることができるので、時間に余裕のあるときは立ち寄ってみるのもよいと思います。
因みに帰りの立ち寄り湯で“ぶなの湯”に入るつもりの方は、最終受付時間が17時なので、間に合うように下山したいところです。
↑ 西丹沢自然教室に戻ってきました
【↓】 “本棚” ~ 帰路寄り道①
“本棚ほんだな”は流量、落差ともに丹沢山地最大級の大滝と評される名瀑です。
日本登山体系などでは落差70mと記されています。
エキスパートは登攀に挑まれますが、右岸の大高巻きは踏み跡も比較的明瞭。
西沢本棚沢そのものは、大滝を高巻けば、それほど難しくはない初級の沢ルートです。
短い距離のなかに沢の面白さが凝縮され、詰めも比較的容易なので、初級者のステップアップに最適です。
【↓】 “下棚” ~ 帰路寄り道②
“下棚しもんたな”は本棚沢よりも800mほど下流で西沢に注ぐ下棚沢にある大滝で、男性的で豪快な本棚に対して、スラブを優雅に流れ落ちる女性的な美瀑として知られます。
日本登山体系などでは落差40mと記されています。
因みに“しもんたな”というのは、本棚に対して“しも”にある棚、下の棚(しものたな)からきているようです。
下棚沢は、下棚以外にもナメの連瀑をはじめ見所が多く、短いながらも登攀的な遡行が楽しめる西丹沢屈指の佳渓。
本棚沢遡行よりも少し距離は長くなりますが、下山もそんなに大変ではないので、日帰り遡行ルートとしてリストアップしておきたい渓でもあります。
1 中川川流域
西丹沢の沢登りを丹沢湖を起点として考えると、東に“花形”ともいえる玄倉川流域、北に大滝を数多抱く中川川流域、西に静寂に包まれた世附よづく川流域に分けることができます。
このうち中川川流域は、主に檜洞丸から畦ヶ丸にかけての相甲国境稜線より南の水を集めて南進する川で、その支流の渓には「本棚」「下棚」「地獄棚」「雨棚」「モロクボ大滝」「白石の滝」など名だたる大滝が散りばめられています(※ 丹沢では大滝を“棚”と表現します)。
日本登山体系では、「湯ノ沢」「悪沢」「箱根屋沢」「大滝沢本流(鬼石沢)」「沖箱根沢」「地獄棚沢」「押出し沢」「東沢本棚沢」「西沢下棚沢」「西沢本棚沢」が紹介されていますが、これ以外にも「マスキ嵐沢」「モロクボ沢」「雷木沢」などの初級ルートもあり、今回私が遡行した「モロクボ沢」のように上流部がいくつもの沢に細分化されていく渓もあります。
2 モロクボ沢
関東で盛夏の水遊びといえば必ず名前の挙がる“白石沢モロクボ沢”。
畦ヶ丸北面の原生林から湧き出す豊富な流れのなかに、美しい釜やナメと、苔むしたゴーロが光彩を放つ西丹沢を代表する癒し系の沢として知られます。
沢登りとしては初級ルートであり、初めての方が水と戯れる楽しさを味わうのにも大変適しています。
都心から比較的近く、アプローチも容易、しかも立派な大滝や美しい釜をもつ穏やかな渓は関東では大変貴重であるように思えます。
モロクボ沢と言えば、何といってもシンボルである“モロクボ大滝30m”が有名。
30mながら大水量を叩き落とす豪快な大滝で、滝下に立ってマイナスイオンを全身に浴びれば、誰もが爽快な気分に浸ることができるでしょう。
軽登山靴で滝見物に来られる方も多いようです。
直登は人工登攀となるものの、右岸高巻きは分かりやすく、岩の隙間を腕力で攀じ登ります。
モロクボ沢の核心部は前半。見所は大滝に始まり石積堰堤まで続く美しい釜と連瀑の饗宴。
短いながらも豊富な水量と戯れることで、真夏の茹だるような暑さをひととき忘れることができます。
大人数ならばここでゆっくりと時間を使い、美しい釜のなかを泳いだり、滑り台を楽しむのもよいのではないでしょうか。
3 上流部 ~ 詰めと下山
モロクボ沢は中流部で水晶沢を左岸に分けますが、本流後半は単調な苔むしたゴーロ歩きとなり、源頭部の渓相は複雑になっていくので、本流よりもむしろ支流に遡行価値を見出すべきかもしれません。
マニアックながら細分化すると、詰めのルートには本流のほかに、水晶沢左俣、同右俣、キメ岸沢、越場ノ沢、滑棚沢左俣、同右俣があり、なかでもシャガグチ丸へ詰める滑棚沢はその名の通り美しいナメ滝が続きます。
核心だけを満喫する最短コースとしては、越場ノ沢から善六ノタワへ詰めるのがオススメです。
どの沢を詰めどのルートで下山するか、モロクボ沢遡行では沢山の選択肢があります。
シャガグチ丸や水晶沢ノ頭のある甲相国境尾根に詰め上がった場合は、一般登山道である白石沢コースか、バリエーションとして水晶沢ノ頭より雷木沢右岸尾根を下降することになりそうです。
また畦ヶ丸や善六山(1,119m)のある右岸に詰め上がった場合は、一般登山道である畦ヶ丸西沢コースか、バリエーションとして善六山→塩地窪沢ノ頭と進み、入渓点近くに降りる塩地窪北尾根ルートを選ぶことができるでしょう。
ルート選択は、起点を用木沢出合ゲートにするか、西丹沢自然教室にするかによって変わってくることになります。
マイカー利用なら前者、交通機関利用なら後者となるでしょうか。
※ 西丹沢登山詳細図(吉備人出版)を参照させて頂きました。
4 アプローチ
【交通機関利用】
富士急湘南バス新松田駅発西丹沢自然教室終点下車(乗車時間70分)。
入渓点まで徒歩約40分。
富士急湘南バスの時刻表はこちらをご覧ください
【マイカー利用】
国道246号清水橋交差点から北上。県道76号山北藤野線で西丹沢自然教室まで。
無料駐車スペース20台ほど。
さらに用木沢出合ゲートまで進入可能。ゲート前に8台ほど駐車スペースあり。
途中に道の駅山北があります。
【↑】 用木沢出合ゲート前
5 立ち寄り湯の情報など
ご参考にして頂ければ幸いです。
中川温泉 ぶなの湯の情報はこちらをご覧ください
西丹沢自然教室の公式サイトはこちらをご覧ください
最後までご一読いただき、有難うございました。
※ HTMLを使用したレポート掲載については許可を得ております。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。