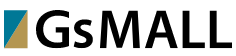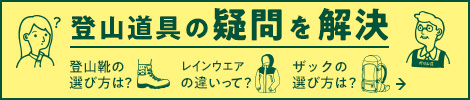厳冬 地蔵岳 ~ ドンドコ沢の氷瀑を巡る (南アルプス鳳凰三山)
- 投稿者
-
伊藤 岳彦
横浜西口店
- 日程
- 2017年01月25日 (水)~2017年01月26日 (木)
- メンバー
- 単独行
- 天候
- 晴
- コースタイム
- 御座石分岐(45分)青木鉱泉(140分)南精進ヶ滝(90分)白糸滝(60分)五色滝(100分)鳳凰小屋(90分)賽ノ河原(15分)赤抜沢ノ頭(60分)鳳凰小屋(240分)青木鉱泉(45分)御座石分岐
- コース状況
- 本文をご参照ください
- 難易度
-


感想コメント
厳冬地蔵岳
ドンドコ沢で氷瀑を巡りながら、大展望の広がる地蔵岳へ。
快晴に恵まれた南アルプスでとても静かな冬山登山を楽しんできました。
特に山頂から望む北岳の偉容は他に比類のない素晴らしいもの。
地蔵岳厳冬の世界の美しさを感じて頂ければ幸いです。
2017/1/25(水) 晴
御座石分岐[10:43]…青木鉱泉[11:30]…南精進ヶ滝[13:50]…岩小舎幕営地[15:36]
2017/1/26(木) 晴
幕営地[7:28]…白糸滝[8:06]…五色滝[9:05]…鳳凰小屋[10:48]…賽ノ河原[12:21]…赤抜沢ノ頭[12:36]…鳳凰小屋[13:38]…幕営地[15:27/16:14]…青木鉱泉[18:29]…御座石分岐[19:17]
豪快な展望広がる地蔵岳へ
国道20号から望む地蔵岳の岩塔は一見近いように見えて、実際に登るとその標高差に思いのほか苦労させられるものです。
雪山初級者でも安心して登れる名山とはいえ、樹林帯の登りのキツさを想像して何となく敬遠してしまうものですが、近頃ラッセル力が頓に落ちてきている私でもちゃんと登頂できることを期待して、何年ぶりかで地蔵岳を訪れてみることにしました。
周知のように鳳凰三山は地蔵仏のオベリスクをもつ山として古くから名山の一つに数えられ、地蔵岳(2,764m)・観音岳(2,841m)・薬師岳(2,780m)の三山から構成されます。
山塊は甲斐駒山脈特有の閃雲花崗岩から成り、その白砂青松の美は秀逸の一言。
もちろん展望にも優れ、甲斐駒から八ヶ岳をへて奥秩父、大菩薩連嶺、さらには御坂山塊から富士山に至るまで一望のうちにありますが、何といっても素晴らしいのは白峰三山の雄姿です。
野呂川の大渓谷を挟んで屹立する3,000m雪嶺の壮観な美しさは、記憶に残るものとなります。
積雪期の鳳凰三山は、マイカー利用ならば、夜叉神峠からの南御室小屋コースと御座石温泉からの燕頭山コースのどちらかを選ぶのが一般的ですが、今回はあえて青木鉱泉からドンドコ沢コースを選択。
積雪の状況によっては結構なラッセルになることも想像できますが、あまり人が訪れることのない沢沿いの静かなコースで氷瀑巡りをしながらゆっくり登る方が面白そうな気がしました。
ドンドコ沢そのものはバリエーション的な魅力を欠き、単なる大滝鑑賞ルートに過ぎないものですが、写真的に絵になる風景に出会えそうです。
ただ御座石分岐から青木鉱泉までの県営林道小武川支線は冬期閉鎖のため青木鉱泉まで車で入れません。
ゲート手前の駐車スペースに車を置かせて頂き、ここからピストンすることにしました。
山梨県の県営林道通行規制情報についてはこちらをご覧ください
南精進ヶ滝を訪れる
国道20号から小武こむ川沿いの林道へ。
御座石分岐までは大部分が舗装されていますが、一部未舗装区間もあります。
今回積雪はなくノーマルタイヤでも問題なく通行することができました。
昭和50(1975)年頃の古いガイドブックによると、穴山橋から平川峠というのを越えて御座石方面に入っていたようですが、それに比べると現在の登山者は随分と楽をしていることが分かります。
御座石分岐のゲート手前には2~3台ほどの駐車スペースがあります。
↑ 青木鉱泉への林道は冬期閉鎖
まずは雪に覆われた林道を黙々と歩き、青木鉱泉へ。
途中小武川に架かる橋の上から薬師岳を正面に望むことができます。
薬師岳への直接通ずる中道の全容を見ることができますが、冬にここを上り下りするのは大変そうな気がします。
↑ 薬師岳を望む
駐車スペースから45分ほどで誰もいない閑散とした青木鉱泉へ。
想像していたよりも雪が少なく、ドンドコ沢方面へのトレースもあります。
これなら何とか頂上まで行けそうな気がしてきました。
↑ 閑散とした青木鉱泉
青木鉱泉からは沢沿いの道をアイゼンをつけずにのんびりと歩いて行きます。
増水時に利用される山回り道というのもあるようですが、入口がよく分かりませんでした。
↑ 雪は多くありません
途中3つほど堰堤がありますが、一番新しいもので平成20年完成とあります。
砂防堰堤なのでやむを得ないのかもしれませんが、静かなドンドコ沢でも開発が奥へ奥へと進んでいる現状に少なからず驚いてしまいました。
↑ 堰堤は左岸越えです
堰堤を過ぎると登山道は沢を離れ、広葉樹林帯をジグザグに登り、やがて長い山腹のトラバースへ。
↑ 枯葉を踏むトラバース
途中枝沢をいくつか横切りますが、大きな氷結はないので、アイゼンなしでも問題なく通過することができます。
↑ 南向きなので明るい
↑ 枝沢を渡ります
↑ 小さな氷瀑
やがて最初のハイライトである南精進ヶ滝に到着。
以前は登山道から離れて滝見台へ立ち寄っていたようですが、現在は滝見台からさらに登り登山道に合流できるようになっているようです。
↑ 南精進ヶ滝全容
↑ 南精進ヶ滝上部
↑ 氷の造形美に目を奪われます
70mクラスの大滝はやはり迫力があります。
滝壺まで降りる余裕がなかったのは残念ですが、中腹から見下ろすだけもその力強さが犇々ひしひしと伝わってきます。
近頃大分冷え込んでいるので、結氷の状態もよさそう。
しかし氷の下では落下する水が依然大きな瀑音を周囲に響き渡らせていました。
ウィキペディアによると、南精進ヶ滝は落差70m、後で紹介する白糸滝、五色滝とともに、“ドンドコ沢の三滝”と呼ばれるそうです。
南精進ヶ滝と、わざわざ“南”を冠していることからも分かるように、一山隔てたところには北精進ヶ滝もあります。
こちらは東日本最大の名瀑と謳われる落差121mの大滝。
地蔵岳の北東面、釜無川に注ぐ大武川の最大支流石空いしうとろ川の中流部に位置し、日本の滝百選の一つにも選ばれています。
↑ こちらは北精進ヶ滝(2015年11月撮影)
折角なので、精進ヶ滝の名前の由来について調べてみました。
精進という言葉は障子に通じ、大岩壁を表わす言葉でもあり、実際滝の両岸には花崗岩の大岩壁が聳え立っています。
また古くから信仰の山である鳳凰山では、行者が途中にこの滝で斎戒沐浴さいかいもくよく(神仏に祈願するために滝の水を浴びて身体のけがれを洗い流すこと)したことからその名がついたとも言われるそうです。
天然の岩小舎で幕営する
南精進ヶ滝を髙巻く感じで越え、しばらく登ると今度は鳳凰滝の滝見台へ至る分岐が現れます。
分岐は登山道上部と下部にそれぞれ道標があり、上部からだと200mを5分のトラバースで行けるようです。
↑ 上部にある分岐
試しに見に行こうとしましたが、意外に雪が深く倒木も多くあり、無駄に時間がかかってしまうので、途中で嫌になりギブアップ。
氷瀑巡りとか言っているわりには軟弱です。
気を取り直して、またしばらく進むと、流水が得られる枝沢を横切ります。
そしてそのすぐ上に、幕営におあつらえむきの天然岩小舎を発見!
まさに私に泊まれと言っているような極上?の空間!
一人用テントを余裕で張ることができます。
ケンシロウばりの行者が一撃でこしらえたものなのでしょうか?
↑ 思わず泊まってしまいました
ちょっとだけ斜めっていますが、雨・風・雪をほぼ防ぐことができて、雪山に来ているというのに下は積雪の全くない砂地。
タクティクス的には鳳凰小屋までは無理にしても、白糸滝を過ぎた辺りにベースキャンプ!?を設営した方が有効なのですが、気が付くと迷わずザックを降ろしていました。
この気温でもすぐ近くで流水が得られるというのは大きい。
ちなみに翌朝-10℃くらいでも普通に流れていました。
地形的にみてここが最後の流水となるのは間違いなく、ここから上では樹林帯のなかでかなり美味しくない水を作ることを強いられそうです。
↑ この枝沢は貴重です
ということで、明日のことは明日考えることにして、今宵はここで過ごすことにしました。
五色滝はとても美しい氷瀑でした
翌日は夜明けとともに出発。
テントに不要なものは全て置いて、軽量装備で地蔵岳アタックです。
特に登山道が氷結している訳ではありませんが、効率よく登るためにアイゼンをつけてスタートすることにしました。
岩小舎から白糸滝までかなりキツイ樹林帯の急登がひたすら続くので、やっぱり昨晩は岩小舎で幕営して正解だったかもしれないと思ってしまいました。
↑ 朝から急登です
↑ トレースがあるので楽でした
急登をじっくりと登ると、“ドンドコ沢の三滝”の一つ白糸滝へ。
滝見台は登山道からわずかに外れたところにあり、非常に開けた空間で気持ちのよいところです。
↑ 白糸滝の全容
↑ 上部をアップで
無雪期ならばおそらく優雅な白糸のような滝を望むことができるのだと思いますが、氷結していると滝なのか、ただの雪壁なのかよく分かりません。
滝よりもむしろ雪が積もった花崗岩のオブジェが美しいと感じました。
朝に作った熱い紅茶を一口飲み、そそくさと先に進みます。
↑ トレースがはっきりしています
↑ 再び樹林帯の急登が続きます
白糸滝に続き、氷瀑巡り最後のハイライトは五色滝です。
道標が立っているところは樹林帯のなかの平地となっており、冬の幕営には最適だと思われます。
↑ 五色滝入口を示す道標
道標のある分岐から五色滝まではトレースもなく、滝の全容を見るためには急斜面を少し下らなければなりません。
調子に乗って滝壺まで下りてしまうと、戻ってくるのが超大変なので、中間部辺りで写真撮影。
↑ 五色滝の全容
↑ 上部をアップで
↑ 氷の造形が見事です
ちなみにこの滝で流水をゲットするのは至難でしょう。
五色滝はドンドコ沢で一番美しい滝と言われるだけあり、とても格調高雅なもの。
この氷瀑を見ることができただけでも登ってきた甲斐がありました。

河原ラッセル頑張りました
ここまでの氷瀑巡りを満喫した後は、いよいよ地蔵岳を目指すことになります。
↑ 美しい原生林のなかを進みます
↑ 稜線がはっきりと見えてきました
再び樹林帯の急登をこなすと、ようやくドンドコ沢の源頭部へ。
↑ 地蔵岳が見えました
↑ オベリスクをアップで
源頭部は明るく開けた河原状になっていますが、数日前の降雪の影響もあり、さすがにこの辺りのトレースはありません。
アイゼンからワカンに換装し、光が強いのでサングラスを装着。
まずは鳳凰小屋を目指し、河原ラッセルに励みます。
↑ ワカンで突き進みます
夏道がどうなっているのか記憶にありませんが、ただ上流に向かって辛抱強く歩を進めるのみ。
時折ハイマツをぶち抜いて、下半身が埋もれてしまうこともありますが、フカフカの新雪ではないので、雪質を冷静に見極めながら進めばそれほど困難ではありません。
それでも結構時間がかかって、ようやく鳳凰小屋に到着。
↑ 鳳凰小屋に到着です
一人くらい登山者がいるかなと思ってましたが、平日だからでしょうか、人の気配は全くありません。
冬期小屋がありましたが、週末は混み合うのでしょうか。
↑ こぢんまりとした冬期小屋
↑ 参考までに内部の様子
北岳の雄姿に感動!
小屋の前でアイゼンに履き替え、いよいよ稜線を目指します。
さすがにメインルートなので、よく踏まれており雪の中に道ができています。
小屋からはしばらく小尾根の急登となり、結構苦しめられます。
↑ 急登をグングンと登っていきます
数日前の降雪の影響でしょうか、あれだけハッキリとしていたトレースも途中でなくなってしまいました。
ワカンは小屋にデポしてきたので、ここはアイゼンのまま強引に直登するしかありません。
↑ そろそろ森林限界を越えます
比較的締まった雪に助けられ、森林限界を越えると、雄大なオベリスクが眼前に聳え立ちます。
↑ オベリスクが見えました
さながら槍沢上部から槍ヶ岳を見上げているかのよう。雰囲気的にも槍の肩直下に似ています。
山頂直下はこんなに傾斜があったんだ、と感心してしまいましたが、雪はよく締まっているので、気持ちよいくらいアイゼンが効きます。
↑ アイゼンがよく効きます
↑ 観音岳を望む
↑ 稜線まで最後の登り
ペツル社のアイゼン=新型バサックを駆使して、ガシガシ登り詰めるとやっとのことで地蔵岳山頂に到着です。
山頂の標識は便宜上なのでしょうか、賽ノ河原に立てられていますが、それにしてもここから望むオベリスクの雄姿は見事なもの。
均整のとれた山容は神秘的な美しさを醸し出しています。
↑ 神秘的なオベリスク
しかし風が冷たすぎて、オベリスク基部へ立ち寄るのを省略してしまいました。
賽ノ河原にはたくさんの地蔵尊が安置されています。
↑ 賽ノ河原
これらは子宝を願うためのもの。赤頭巾を被った一体の地蔵尊が印象に残りました。
↑ 印象的な地蔵尊
また賽ノ河原からは甲斐駒と仙丈が並んで雄大に望むことができます。
↑ 甲斐駒ヶ岳を望む
↑ 仙丈ヶ岳を望む
↑ 八ヶ岳を望む
しかしここまで登ってもまだ白峰三山を見ることはできません。
ここから赤抜沢ノ頭まで最後の登りが待っています。
↑ 赤抜沢ノ頭まで最後の登り
アイゼンを効かして最短距離で直登すると、遂に赤抜沢ノ頭へ。
↑ 赤抜沢ノ頭に到着
そして山頂に立つと......。
↑ 北岳が見えました
正面に望む北岳の雄姿。壮大無比の大景観。久しぶりに感動してしまいました。
↑ 北岳をアップで
↑ 大樺沢も真っ白です
やはり最後山頂に着いたときに大景観が広がるというシチュエーションは、シンプルですが登頂の達成感が一味違うような気がします。
そこに至るまでの労苦が大きければ大きいほど、感激の度合いもきっと強く、激しいものになるのでしょう。
美しく偉大なものに胸が熱くなるという感覚。
心の澱みが全て浄化され、気持ちが生き生きとしていく感覚。
厳冬の南アルプスはそんな感覚を我々に与えてくれる、かけがえのない世界であり続けてほしいものです。

最後までご一読いただき、有難うございました。
※ HTMLを使用したレポート掲載については許可を得ております。
※ 画像サイズはスマートフォンで見やすい大きさに設定してあります。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。