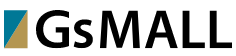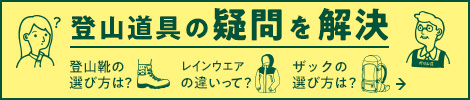トレーニング山行 エクストリーム伯耆大山 弥山(鳥取県)
- 投稿者
-
木德 尚代
グランフロント大阪店
- 日程
- 2025年02月18日 (火)~2025年02月18日 (火)
- メンバー
- 沢の会の会長 女性メンバー1名
- 天候
- 雪 積雪 50CM以上 風速15M
- コースタイム
- 山行
5:15
休憩
2:19
合計
7:34
距離 8.0km 登り 1,041m 下り 1,047m
7:57
2
分
スタート地点
7:59
8:21 スタート (30分待機でした)
2
分
大山寺橋・南光河原駐車場
8:23
4
分
夏山道登山口(大山寺橋側)
8:28
8:31
62
分
夏山登山口
9:33
9:44
21
分
三合目
10:05
10:07
12
分
五合目
10:19
10:21
18
分
行者谷分かれ
10:39
11:12
35
分
六合目避難小屋
11:46
11:52
5
分
八合目
11:57
11:58
18
分
石室方面との分岐
12:16
12:17
1
分
大山頂上避難小屋
12:18
12:21
2
分
大山頂上碑
12:23
13:06
11
分
大山頂上避難小屋
13:17
4
分
石室方面との分岐
13:21
13:24
42
分
八合目
14:06
14:07
30
分
六合目避難小屋
14:36
14:42
3
分
行者谷分かれ
14:45
14:51
13
分
五合目
15:04
15:06
28
分
三合目
15:33
15:34
1
分
夏山道登山口(大山寺橋側)
15:35
1
分
大山寺橋・南光河原駐車場
15:36
ゴール地点
- コース状況
- 山頂小屋 マイナス8.5度 マイナス10度以下 風速稜線 15Mくらいです。
積雪は大山下 で一日で50CM 山はかなりの積雪なりノートレースとホワイトアウトでした
- 難易度
-



感想コメント
大寒波一日目です。
もともと北壁のアルパインクライミング予定ですが、午後からのストームと風を懸念
夏道も敗退かもの覚悟で出発致しました。ログより30分遅くスタートです。
一合からアイゼンもしくはスノーシューで登っていきます。
6合までは順調でした。
6合でアイゼンに履き替えます。5合上の ツリーホールが下りかなり危険予想されます。
いきなりのストームです。ほぼ斜面を登っていきます。
ケルンもほぼ見えない。霧氷がエビのしっぽに変わっておりました。
稜線はほぼホワイトアウトでした。
小屋はぎりぎりまだ扉が開いておりました。
先に弥山に向かいます。
弥山までの体内コンパスはホワイトアウトでも動いておりました。
山頂は本日自分たちのみでした。
小屋にて温かい飲み物などで休憩をとりました。
小屋もマイナス9度です。
さて小屋でて ホワイトアウトが更にきつくなっております。
青ポール(道導に青いポールがあります)を確認しながら下りました。
途中ハプニングありましたが、難を逃れました。
6合からも尾根を一本東に行き、ツリーホールの 穴穴穴に落ちそうになったりと
デンジャラスゾーンは続きました。
ようやく尾根に帰り下ります。膝上くらいの新雪です。
ここは八ヶ岳?なる感もあるほどの一日の積雪量になりました。
下りに班雪洞研修を致しました。
ほぼホワイトアウト、ノートレースに下りになりました。
お一人登ってこられましたが、6合で下ってきてはりました。ベテランの方でした。
無事下山。お疲れ様でした。別山より危険な夏道 との隊長語録
ストーム中、積雪量増加の 2月18日弥山登頂なりました。
ガイド仲間から、無理しないで、死ぬぞ、風みとるんか?などアドバイスありがとうございました。
通常ならば中級の雪山になりますが、厳しいアルパイン雪山になりました。
仲間に感謝です。
下山御の 豪円湯院の 雪の中の露天風呂で癒されました。
16時までならばお鍋セットと入浴料で1000円なります。おすすめです。
ザック オスプレイ カイト48
ギア
ハーネス ビレイデイバイス 各補器 ガチャ 数種類 ロープ40M
アイゼン ペツル ピッケル ペツル クオーク
ヘルメット サングラス 日焼け止め
ワカン 、スノーシュー ライトニングアッセント
ウエア
モンチュラ シェル アクロJk アクロPT ニュウモラップFD
ベースレイヤー ファイントラック ウオーム モンチュラジップアップ
手袋 ミレーのウールベース ブラックダイヤモンド レジェンド ソロイスト ソロイストミトン
バラクラバ ファイントラック 厚手 薄手 二枚
ニット帽、ネックゲーター スマートウール
靴 ネパールエボ スプルテイバ スパッツ イスカ
アライテント ツエルト2
スノーシュー ライトニングアッセント MSR
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。