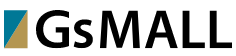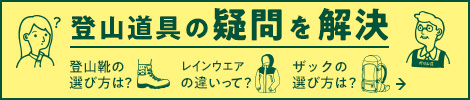KOBE六甲全山縦走大会2013
- 投稿者
- あやや(おとな女子登山部)
- 日程
- 2013年11月10日 (日)~2013年11月10日 (日)
- メンバー
- まっちゃん
- 天候
- 雨
- コースタイム
- 6:00 須磨浦公園駅→6:32 旗振山→6:50 高倉台→7:21 栂尾山→8:01 横尾山→8:58 妙法寺→9:58 高取山→10:54 鵯越駅→11:58 菊水山→13:03 鍋蓋山→13:29 大竜寺→13:50 市ヶ原→15:20 摩耶山→16:35 丁子ヶ辻→17:15 ガーデンテラス→18:09 一軒茶屋→20:50 塩尾寺→21:20 宝塚駅 ※休憩含む計15.2h
- コース状況
- コース自体は、整備され標識も分かり易いです。
大会当日は、要所要所でボランティアの方が誘導して下さいます。
仮設トイレも充実しています。
雨の為、急坂が泥だらけでかなり滑りやすくなっていました。
またガスで日没後は特に視界が悪く、明るいヘッドランプが必要でした。
- 難易度
-


感想コメント
おとな女子登山部のまっちゃんと「KOBE六甲全山縦走大会2013」に参加しました。
完走を目標に、大会の様子や装備などを紹介致します。
①大会の様子
須磨浦公園から6:00スタートしました。
その時は人もまばらで、待つことなく受付を通過しました。
今回は、雨のため5:00前に繰り上げスタートがあったようです。
トレランスタイルが多く見られたのが印象的でした。
空はほんのり薄明るく、ヘッドランプを付けても付けなくても良い位です。
高倉台周辺までは比較的スムーズに動いていましたが、階段手前から停滞し始めました。
前情報通りですが、まとめますと
《込み合う場所》
須磨アルプス付近
菊水山~鍋蓋山
摩耶山の細い登山道
船坂峠~大平山
《比較的スムーズ》
スタート~須磨アルプス手前
妙法寺~菊水山手前
市ケ原付近
六甲山頂一帯
とにかく狭い、急坂、岩場、暗がりでは自分のペースで歩くことはできません。
練習よりもかなり時間がかかるものと思っておいた方が気が楽です。
雨の為、結局ほぼ最後まで渋滞が起きていました。
②装備
数日前から、ずっと天気予報が良くなかったのである程度覚悟していましたが
雨は降ったりやんだりで、想像していたよりはマシでした。
まず、服装は暖かめで準備。
行動中、以下のものを使用しました。
■トップス
長袖アンダー
長袖ウール
ウィンドストッパーのベスト(寒い時+日没後)
レイン上(随時)
■ボトムス
サポートタイツ
オールシーズン用パンツ
レイン下
■靴
ミッドカットの登山用シューズ
簡易レインの方を見ていると、やはり自分の汗で結露して中が濡れていました。
また、日没後懐中電燈を持つと片手が塞がれ、急坂でバランスを崩す姿を多く見ました。
近くに人が多いと問題ないのですが、単独だと明るいヘッドランプ(推奨100ルーメン以上)が必須です。
次に、ごはんのこと。
雨だったこともあり、特に休憩場所(主にチェックポイント、頂上付近等)が混み合いました。
座って食べるのは結構難しい。。。
また、ザックカバーをしていると、なかなか荷物を広げる気にならないので
片手で食べられるものをチョイスした方がよいかと感じました。
飲食は、体型や各自による部分が大きいので参考程度にして下さい。
日没後は、ほとんど消費しませんでした。
途中、飲み物が手売りで販売されているので、自販機が売り切れでも
どこかで入手することができると思います。
六甲山頂以降は売り切れはありませんでした。
《消費行動食》計約1840kcal
※カッコ内は(総計・約キロカロリー)です。
おにぎり×2(330)
おはぎ×1(180)
たまごスープ×1(70)※差し入れ分
カロリーバー×1(200)
ソイジョイ×2(270)
アミノバイタル×2(360)
ウィダインゼリー×1(180)
チョコ 40g(250)
《消費水分》計2L
・装備分
水 1L クエン酸水 200/400mL
・補充分
お茶 300mL ホットレモン 500mL
③おまけ 終わったら・・・
その日はストレッチをして、ゆっくり眠るに限ります。
アミノ酸を摂取すると、疲労回復が早いのでお勧めです。
そして、使った道具のお手入れを。山道具の寿命は「ケア次第」です。
・レインウェアは、そのままにせず洗濯しましょう(※洗濯タグを確認してから!)
専用の洗剤ですと、洗剤分の残留が残りにくいです。いつもよりすすぎを多めにするのがポイント♪
・汚れた靴は、まず中敷きを抜きます。
ブラシで汚れを落として、取れないものは水で流します。
陰干しで良く乾かして、最後に防水スプレーをかければ完璧。(※素材に注意して下さい!)
・ポールを使用したら、分解して乾燥しましょう。
中が濡れていると、パーツが腐食してしまいます。
他、ご不明な点はスタッフまで★
最後に・・・
ボランティアの皆様が各所おもてなしをして下さったり、あたたかい応援をして下さったりと
陰で支えて頂き本当に感謝です。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。