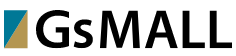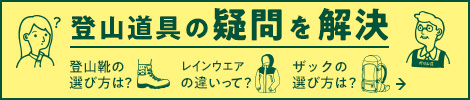裏那須の美渓 井戸沢 ~ 美瀑とナメが続くコンパクトな渓を辿る(苦土川支流 流石山南面)
- 投稿者
-
伊藤 岳彦
横浜西口店
- 日程
- 2017年06月15日 (木)~
- メンバー
- 単独行
- 天候
- 曇
- コースタイム
- 大川林道終点ゲート(45分)三斗小屋宿跡(30分)堰堤から入渓(65分)二俣(70分)稜線登山道(40分)大峠(110分)大川林道終点ゲート
- コース状況
- ※ 本文をご参照ください
- 難易度
-

感想コメント
井戸沢
那須岳の西側にある井戸沢は、明るく開豁な美渓としてとても人気があります。
アプローチが比較的良く、前半部に直登できる滝、後半部にナメ滝が数多くあり、短時間で充実した遡行を楽しめるところが魅力です。
生憎の空模様でガスがかかっていましたが、滝を登る楽しさが随所に散りばめられ、飽きさせない渓相が印象に残りました。
2017/6/15(木) 曇
大川林道終点ゲート[11:42]…三斗小屋宿跡[12:28]…堰堤から入渓[13:01]…二俣[14:06]…稜線登山道[15:15]…大峠[15:54]…大川林道終点ゲート[17:44]
■ 三斗小屋宿跡まで歩く
井戸沢は裏那須を代表する美渓。
アプローチが比較的便利で、南面の明るい渓相を短時間で遡行できるためとても人気があります。
前半部は樹林帯のなかに直登可能な滝が多くあり、後半部は開放的なナメ滝が広がる変化に富んだ渓相。
那須五岳の一つ、三本槍岳の西側にある、流石山から大倉山にかけての稜線を水源として南下し、那珂川水系の苦土にがと川(湯川)に、三斗小屋宿跡付近で注ぎます。
那須連峰の沢として広義では認知されているのかもしれませんが、日本登山体系では裏那須あるいは奥那須とも呼ばれる男鹿おが山塊の項で紹介されており、井戸沢以外に苦土川流域では大沢左俣・大沢右俣・西沢も遡行価値の高い渓として推奨されています。
那須連峰の沢は阿武隈川源流に代表されるものであり、井戸沢を那須の沢とみなすのは、厳密には避けるべきなのかもしれません。
東北道黒磯板室ICから県道369号線を辿り、深山湖へ。
地下発電所展示館を過ぎてさらに先、県道から北に延びる大川(白湯山)林道に入ります。
林道は未舗装のダートですが、四駆でなくても通行に支障はありません。
途中林道七千山線を左に分け、【三斗小屋宿跡⇒】の道標に従って進むと間もなく終点。
湯川にかかる橋にゲートが設置されています。
↑ 林道終点にある標識
ゲートすぐ手前に2台ほどの駐車スペースしかありませんが、少し手前の路肩にはまだまだ駐車できそう。
ただし落石が多いので、停める場所には注意したいところです。
ゲートをくぐり、まずは入渓点まで小1時間の林道歩き。
↑ ゲートから出発
北側が原生林、南側が植林の林道は広くて歩きやすいですが、熊が出没するところなので、鈴を鳴らしながら進みます。
↑ 広くて歩きやすい道
沼原湿原分岐を左に進み、しばらく歩くと三斗小屋宿跡へ。
ここは戊辰戦争による惨禍の爪跡が残る場所。
歴史を感じさせる墓碑、石仏、石像などが幾つもありました。
↑ 古そうな墓碑
↑ 三斗小屋宿跡
↑ 案内板①
↑ 案内板①
三斗小屋宿跡の少し先が、本当の林道終点。
三斗小屋温泉関係者の方のものでしょうか、車が4台停められていました。
ここは三斗小屋温泉への登山口にもなっています。
↑ 三斗小屋温泉方面の道
また林道終点の左奥右手には、大峠方面に直接通じる会津中街道があり、今回はこの道をわずかに辿って井戸沢に降りました。
↑ 左は林道行き止まり 右が会津中街道
井戸沢出合は伏流しており、何もない涸れた状態です。
↑ 井戸沢出合は伏流
少し上流へ進むと、木製の堰堤があり、この堰堤から遡行が始まります。
↑ 堰堤が見えてきました
堰堤は左手のトラロープを使って越えることができます。
↑ 堰堤は左から越えます
↑ 堰堤上で入渓準備
堰堤の上で準備を整え、いざ入渓。
↑ 入渓点より
空はどんよりと曇り、あまりテンションが上がりませんが、気合を入れて出発です。
■ 直登可能な滝が沢山あります
井戸沢の前半部は樹林帯の中に登れる滝が多くあり、大変面白いところ。
特に核心となるところもなく、幾つもの美瀑を軽快に登っていくことができます。
↑ 最初の3m滝
やがて現れる15m末広の滝は、おそらく井戸沢の中で最も美しい滝。
↑ 15m末広の滝
この滝は登れないので、左岸リッジに取り付き、樹林帯まで登ります。
↑ 左岸リッジ
傾斜がかなりきついので、やはり残置ロープに頼ってしまいます。
↑ 残置の様子
残置を利用してフンフンと体を持ち上げ、さらに樹林帯の中へ。
笹の中の踏み跡は明瞭で、沢への下降もロープ不要です。
↑ 沢へ降ります
次に現われる顕著な滝は10×15m滝。
↑ 10×15m滝
↑ 上部の様子
上部は水流沿いに登ることもできそうでしたが、左岸に岩のトンネルがあり、珍しかったのでここを通過しました。
↑ 岩のトンネルを登りました
続いては容姿端麗な15m滝。
↑ 15m滝は右壁を登りました
左の水流沿いを登るか、右壁を直登することができます。
↑ 中段のバンドから上を見上げる
↑ 水が勢いよく流れていきます
さらに続いて10m滝。右岸を登ります。
↑ 10m滝
↑ 右岸の様子
その上は10×20mのナメ床。水流沿いに登っていきます。
↑ 10×20mのナメ床
さらに進むと、前半のハイライト18m滝。
↑ 18m滝が見えてきました
↑ 18m滝
この滝は赤茶色の層状になった岩盤の左壁を軽快に登ることができます。
↑ 左壁の様子
↑ 右壁はこんな感じです
その先も登れる小滝が続き、ほどなく二俣に到着です。
↑ 二俣に到着
二俣は1:1。ルートは右になります。

■ 雪渓の通過に手こずる
二俣を過ぎると、渓は徐々に開け、傾斜のあるナメ床が続くようになります。
↑ 傾斜のあるナメ床
晴れていれば青空の下、開放的な風景にきっと心が躍るのでしょう。
しかしこの日は生憎の空模様で、テンションは下がる一方。
ガスが立ち込め、稜線はおろか今いる滝の上がどうなっているのかさえもわからない状況です。
さらに追い打ちをかけるようにテンションを下げさせたのは、沢を埋める雪渓。
↑ 雪渓が現れます
さすがに6月の那須の沢沿いには雪渓があるんですね。
どうりで水が冷たいわけです。
雪渓を避けて右岸斜面を登ることもできそうですが、おそらく笹藪漕ぎで四苦八苦しそうな感じ。
ここは忠実に沢を詰めた方が効率がよさそうです。
しかし雪渓の通過は意外に大変なもの。
雪渓の端を慎重に歩いたり、雪渓の下を匍匐前進したりして沢を詰めますが、時にはスノーブリッジがいきなり崩れることもありました。
↑ 雪渓をくぐります
斜度のある雪渓では軽アイゼンが欲しくなりましたが、何とか無事に雪渓を突破。
最後は源頭部の窪を詰めると笹藪となり、わずかな藪漕ぎで登山道へ。
↑ わずかな笹藪漕ぎ
結果的に2時間強の遡行でしたが、内容的にはとても充実したものでした。
帰路は一般登山道をまず大峠まで。
↑ 大峠へ下ります
この辺りはとても開けた草原状で、7月はニッコウキスゲの花畑になるそう。
この日はガスが濃く何も見えませんでしたが、花の咲く季節に一度は訪れてみたいものです。
また大峠は歴史ある会津中街道の最大の難所であり、戊辰戦争時は新政府軍の大砲がここを越えたということですから、とても驚きです。
ちょっと歴史を紐解いてみると、1868年10月8日(慶応4年8月23日)、三斗小屋宿に進撃した新政府軍は、会津藩の青龍足軽四番隊・青龍寄合二番隊と交戦。
激闘の末、会津軍は大峠を越えて会津領へ敗走。
新政府軍は追撃のため、大砲を大峠に運び上げ、会津領に進軍したとのこと。
因みにこの日は、白虎隊が城下に立ち上る煙を落城と勘違いして飯森山にて自刃した日でもあるそうです。
大峠からは三斗小屋温泉へ続く登山道を辿り、峠沢まで。
峠沢を渡渉してしばらく進むと、【三斗小屋宿跡⇒】の道標があります。
↑ 分岐に道標あります
これが会津中街道の分岐点。
会津中街道についてはこちらをご覧ください
地図には記載されていませんが、歴史があるだけに踏み跡は明瞭です。
三斗小屋宿跡まで数回の渡渉を交えながら導いてくれます。
↑ 渡渉もあります
↑ とても歩きやすい道でした
三斗小屋宿跡まで戻ってくると、夕立に遭遇。
どのみち水陸両用の沢装備なので、ゲリラ雷雨もウェルカムです。
気持ちのよいシャワーを浴びながら、歴史を感じさせる廃村を後にしました。
帰りの立ち寄り湯は板室温泉へ。
最終受付18:30にギリギリ間に合いました。
板室健康のゆグリーングリーン(第4水曜休)の情報はこちらをご覧ください
最後までご一読いただき、有難うございました。
※ HTMLを使用したレポート掲載については許可を得ております。
※ 画像サイズはスマートフォンで見やすい大きさに設定してあります。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。