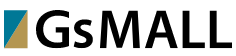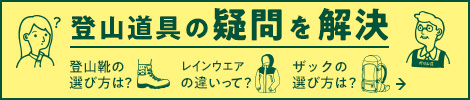休館日に金時山へ~気温とテンション高めでした~(神奈川県)
- 投稿者
-
浅見 直紀
さいか屋藤沢店
- 日程
- 2018年02月14日 (水)~2018年02月14日 (水)
- メンバー
- 松尾SM
大人女子登山部くみんちゅ
町田店アルバイト5名
- 天候
- 晴朗なれど風強し
- コースタイム
- 金時ゴルフ練習場→(40分)→宿り石→(75分)→金時山山頂→(80分)→金時山登山口
- コース状況
- 稜線は雪と霜が解けてぬかるんでいた。
山の下部・上部は圧雪されて氷結していたので、アイゼン持参推奨します。
- 難易度
-

感想コメント
気付いたら2月。未だに山に行っていない状態の中、暫くぶりに行けた。
休館日を利用して、町田店メンバーで金時山へ。登山学校の実技下見を兼ねての山行だが、何はともあれ初登り。先月末から思いっっっ切り体調崩したので、色々とドキドキだ。主に体力だけど。
箱根湯本駅からバスの予定だが、思ったよりも御殿場アウトレットへ向かう観光客が多くて断念し、タクシーで金時神社入り口まで。ちなみにセダンタイプで4,800円。トイレが完全凍結していたり、ボトルの漏水で騒いだりしたが、ウダウダ準備して出発。
早速雪だ。この日は寒くなく、快適に歩ける。しかし、金時神社をちょっと過ぎた辺りで氷結具合が想定以上だったため、アイゼン装着を決意。6本爪アイゼンを持参したが、装着は実に5年ぶりだ。地面のザクザク感が堪らんです。松尾店長も踊るようにステップして感触を堪能しておられた。
うちの若ぇ衆は先頭で雪合戦チックなことをしだす。若いって素晴らしいね。あんな時もありました。カメラに雪が当たって修羅場に片足を突っ込んだりしていたが、若さ故の過ちか!
さて、日当たりの良い場所は雪が少なかったり、むしろぬかるみ具合が凄かったりしたが、アイゼンは着けたまま、宿り石に到着。大きな氷柱が何本も出来ていた。こういうの見ると壊したくなるんだよねぇ、とガツンガツンやっていたら何故か若ぇ衆から「荒ぶってる」と形容される始末。フツーですよぅ?
で、宿り石を過ぎて90度方向が変わった辺りから、日差しが強烈になりだした。風が無くて気温が高ければ暑くなるのが道理ってもんです。この辺りから先頭集団と後方集団に別れ気味になる。先頭の平均年齢が低すぎて話に着いていけなくなったのではなく、暑いからです。一部へ言い訳をしておきます、えぇ。ちなみに私は後方集団だった。あまりに暑くて雪を手に持ってポンポンしていたら「浅見が狙ってる!」とか、再びの謂れなき誹謗に晒された。
「サーティーンなスナイパーみたいだな(松尾)」「後ろに立ったらヤバイっすよ(私)」「あっ!やっべ!(松尾)」
で、山頂。天気は相変わらず良く、富士山から芦ノ湖まで丸見え。南アルプスとかもバッチリ。さぁ飯だ!
今日の昼飯は、新しく店に入れた、お湯を注ぐ系のフリーズドライ食品の試食を兼ねていた。色々と食べさせてもらったが、どれもハズレは無かった。と言いますか、好みにドンピシャだった物もあった。食うのに夢中で、写真忘れたことに帰りの電車の中で気付いた程だ。そんな美味そうな匂いにつられて猫も寄ってきた。あまりの愛嬌に危うく日本語を忘れそうになったが、丁度良いタイミングで、くみんちゅが用意してくれたチョコフォンデュが完成したので助かった。イチゴとマシュマロとバナナの黄金トライアングルには勝てないな!とか思って居たら、茹でた餅というダークフォースが現れて一同を混乱させたのだった。一度お試しあれ。かなりイケます。
ここまでが快適な記憶だった。
実は調理中から風が異常に強くなりだして、寒さで発狂しそうだったのだ。ここで私のウェアを参考までに記録しておくと、
上:アンダー+ウールシャツ+化繊インサレーション+ウィンドブレーカー+ネックゲイター+ビーニー
下:アンダー+ウールタイツ+登山パンツ
以上、厳冬期の八ヶ岳にヤッケとオーバーパンツがあれば登れる状態でしたー。
お解り頂けただろうか?これでも震える異常な寒さ。
あまりの風の冷たさに足をツるメンバーも出た。帰宅して知ったのだが、この日は春一番観測の日だった。道理で強かった訳です・・。これはいかん!と小屋で少し休憩して退散。帰りは往きの状態から推察して、アイゼン無しで。下りに不安があるメンバーはストックを使用して行く。矢倉沢峠への分岐までが雪で、そこから先は基本的にぬかるみだったために正解だったと言えるだろう。夢中で降りて、気付けば別荘地に入っていた。国道を渡った先にある公衆トイレ前に泥落としの水道があったので、有り難く使わせてもらう。身綺麗にした後で、小田原行きのバスで帰ったのだった。
最後に、小田原行のバスも混んでいて、箱根湯本駅まで立ったままだったため、山道でかなり振り回された。バス利用の際には留意したい点だと思った。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。