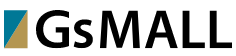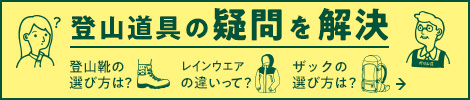西丹沢の美渓 小川谷廊下2019 ~ 魅惑のゴルジュを抱く清冽な渓へ (玄倉川支流)
- 投稿者
-
伊藤 岳彦
横浜西口店
- 日程
- 2019年06月18日 (火)~
- メンバー
- 友人1名
- 天候
- 晴時々曇
- コースタイム
- 入渓点(75分)大岩(30分)石棚下(60分)東沢出合
- コース状況
- ※ 本文をご参照ください
- 難易度
-

感想コメント
小川谷廊下
丹沢随一の美渓と謳われる小川谷廊下。
関東の沢登りスポットとしては、最も人気の高い超メジャーな渓です。
比較的短い流程のなかに、易しすぎず難しすぎない滝が連続。
シンボリックで興味深い見所が飽きることなく随所に散りばめられています。
初夏の青空のもと、水量豊富な渓で爽快な一日を過ごしてきました。
2019/6/18(火) 曇時々晴
入渓点[8:23]…大岩[9:30]…石棚下[9:53]…東沢出合/遡行終了点[10:59]
■ 心のリセット
時には四六時中仕事に追われることもありますが、たまには余暇を楽しむことも人には必要です。
リラックス、リフレッシュ、リセット…表現は何でもよいですが、純粋に何かを楽しむことで思考が活性化し、前向きな気持ちをもつことができます。
とりわけ登山は、肉体と精神の両方を充実させ、心地よい疲労感とともに、何物にも変え難い達成感を我々に与えてくれます。
私にとっては、沢登りこそが心のリセットに必要不可欠なもの。
ただ戯れるだけで、日々の雑念を雲散霧消させてくれる清流。
脚だけでなく、上半身も目一杯に使うことで感じられる適度な疲労感。
時には危険個所から生還するために敢行するデッドオアアライブな行為。
暗闇のなかでただ焚火を見つめ、人生の目標や方向性について思念する時間。
それらが私の心にもたらすパワーは本当に不思議なものがあります。
今回訪れたのは、沢登りド定番の小川谷廊下。
私にとっては4年ぶりの来訪ですが、細かい記憶がほとんど飛んでしまっています。
友人と一緒に、初めてチャレンジするような気持ちで、とても楽しい遡行を満喫することができました。
西丹沢の水系は丹沢湖を基点に、東に玄倉くろくら川、北に中川川、西に世附よづく川に分かれます。
中でも玄倉川は、鍋割山から檜洞丸まで、丹沢主脈でぐるりと囲まれた山域の全ての水を集める大渓谷で、花崗岩や石英閃緑岩から構成される明るくも険しいダイナミックな渓谷美は秀逸の一言。
今回訪れた小川谷は、懐にブナの原生林を抱く同角山稜を源として南進する渓で、玄倉川の一大支流です。
小川谷廊下とわざわざ廊下と名前がついて紹介されるのは、清涼感溢れるゴルジュが連続するためなのでしょう。
ゴルジュ内に飽きることなく続く手頃な滝をグングンと乗り越えていく楽しさは、この渓の大きな魅力になっています。
■ 堰堤を梯子で下る
交通機関利用、マイカー利用ともに玄倉が起点。
玄倉には広大な無料町営駐車場があります。
↑ 玄倉駐車場から出発
一時 “ユーシンブルー”により賑わっていた玄倉駐車場も、2017年の玄倉林道崩落により、元の静けさを取り戻したように思えます。
近年、玄倉川橋より80m先にゲートが設置されましたが、この日は開放中。
↑ ゲート開いてる!
以前の状態に戻ったのかもしれませんが、我々は予定通り歩くことにしました。
玄倉から立間大橋を経て、穴ノ平橋手前までは小1時間ほど。
↑ ここは左 仲ノ沢林道へ
看板に記されていますが、仲ノ沢林道(小川谷右岸林道)は、7月1日から9月30日まで神奈川県公安委員会規制により、通行許可の無い車両の通行は禁止されており、夏のハイシーズン中ここは閉鎖されるはずです。
↑ 立間大橋
沢へ降りるポイントはカーブミラー手前のケルンが目印となっているようです。
↑ ここから沢へ降ります
なお、小川谷へ降りるには2つのルートがあります。
① ゴカイ沢へ下り、堰堤を4つほど梯子下降していくルート
② 植林帯の急峻な踏み跡を辿って、河原に直接下りるルート
靴を濡らしたくないなら②ですが、初見ではやや分かりにくいように思えます。
なお最下部の急峻な斜面には固定ロープが張ってあります。
我々は梯子をガンガン下る①を選択。
途中沢の中を歩く感じになるので、沢靴に履き替えてしまってもよいでしょう。
靴下を濡らさないように歩くのは、少し神経を使います。
↑ 堰堤は梯子で下ります
15分ほどで広々とした河原に出ました。
↑ 河原で入渓の準備をします
■ 難しい滝は高巻き
さて、いよいよ入渓!
空は晴れ上がり、気温も徐々に上がってきているのが分かります。
↑ いい天気です
入渓してすぐに現れるのが2m滝。
↑ 2m滝
右から攀じ登りますが、上部はややハングしています。
上がってみると、リング状の残置支点が取り付けられていました。
続いてすぐ先に、大岩のある5mCS滝。
↑ 5mCS滝
通常は右から。立派な残置スリングが取り付けられていますが、水量が多いと登るのは難しいと思われます。
ちなみに、以前は流木や梯子があったそうです。
↑ 右側に残置スリング
上級者は左の水流に取り付き、水流中のスタンスを手がかりに、水流に落とされないように突っ張りで強引に突破するそうです。
↑ エキスパートは左から
さて我々はというと、無難な高巻きを選択。オジサンは無理をしません。
巻きは左岸。最初の滝上から斜面を這い上がりますが、何となく踏み跡があります。
↑ 最初の滝上から高巻きへ
少し上から今度はトラバース。
そうすると意外にも明瞭な踏み跡があり、植林の防護柵まで現れます。
↑ 上部にある作業道
↑ 途中のトラバースは慎重に
その先で急峻なルンゼ状をロープなしで下降すると5mCS滝上に降りられました。
↑ 最後はルンゼ下降
沢へ戻ると、今度は6m滝。石英閃緑岩を流れ落ちる美しい斜瀑です。
↑ 6m滝
登路は左。ホールド豊富で容易に登ることができます。
↑ ここを登ります
ここからしばらくはナメ交じりの穏やかな渓相を進みます。
続いて現れるのが、立派な2段7m滝。
↑ 2段7m滝
2段目はちょっと高度感のある登りとなります。
↑ 2段目に取り付きます
水流の左を登ると小さなバンドがあり、そこから今度は左上に斜上。
水量が多いと厄介な滝かもしれません。
その先は比較的穏やかな渓相。
初夏の陽射しを浴びながら、無心で渓を辿ります。
再びゴルジュとなり、今度は6m滝が立ちはだかります。
↑ 6m滝
上級者は右壁をへつって越えていくそうですが、我々にはとても無理なので、躊躇なく右から巻きます。
↑ 右から巻きます
↑ 途中に残置スリング
↑ 足場はしっかりしています
スラブ状のゴルジュを越えると、裏見のできる3m滝へ。
滝の下を左から右へ潜って、右壁を登ります。
■ 石棚のゴルジュは水量豊富
続いて現れるのは小川谷名物と言われる大岩。
↑ これが大岩
そのまんまの名前ですが、どでかいツルツルの大岩の斜面を、残置ロープを掴みながら力任せに登ります。
↑ 斜度はそんなにキツくありません
素朴な疑問で、もしも残置ロープがなかったらどうするのか調べてみたところ、大岩の下を水流沿いに越えることができそう。
しかし、全身ズブ濡れになるのを覚悟しなければなりません。
↑ 大岩の下はこんな感じ
↑ ズブ濡れになれば、越えられそう
大岩を過ぎると、僅かながら渓相は穏やかなものになります。
やがて渓が狭まってくると、いよいよ核心部である石棚のゴルジュに突入します。
↑ 石棚のゴルジュ入口
昔はこの辺りの淵ももっともっと深かったそうですが、今ではほぼ埋まってしまい、問題なく通過することができます。
確かに登山体系では『釜は深い』『難関』という記述を見ることができます。
↑ 深い釜ではありません
↑ 無心で突き進みます
やがて小さいながらも迫力のある滝が現れます。
登路は左。見た目以上にホールドがあり、快適に登ることができます。
時期的に水量も多く、水の流れも速いように思えました。
↑ 迫力ある小滝
↑ 左側を登ります
それにしても核心のゴルジュの美しさは実に秀逸。
ちょうど陽が差し込み、清流が光り輝くように見えます。
躍動する水の幻想的な動きがとても印象的でした。
途中右岸から滴り落ちる大コバ沢を見送った後も、ゴルジュ内に小滝が続きます。
↑ 大コバ沢出合
■ 石棚を越えて
やがて2段20m滝石棚が眼前に姿を現します。
小川谷の盟主とも言える、本日のハイライトです。
↑ 石棚の雄姿
↑ 大きさ伝わりますか?
石棚は逆くの字型のとても美しい滝で、その豪快さが印象的です。
ちなみに丹沢では、“滝”を“棚”、“沢”を“洞”、“山”を“丸”と呼ぶなど、独特な言い回しが定着しています。
さて登路ですが、直登は不可。
↑ 高巻きは右岸の岩塔
右岸の岩塔を20mほど登ると上部テラスに上がることができます。
↑ 登路はこんな感じ
結構急峻ですが、フリーで難なく登ることができます。
↑ 足場はしっかりしています
上部に残置ボルトがありますが、大分古いものでした。
上部テラスへ上がったら、今度は右の緩い斜面をトラバースして、沢へ戻ります。
↑ トラバースは慎重に
以前訪れたときは、石棚の上から美しいコバルトブルーの釜が見えた気がしたのですが、今回は透明な釜しか見えず、ちょっとガッカリしました。
■ フィナーレは石積み堰堤
その先上流部へ進むと、やがて癒し系の渓相になっていきます。
釜や淵、小滝、トイ状、ナメが交互に現れ、気持ちの良い遡行が楽しめるところです。
小デッチ沢、大デッチ沢を分けながら忠実に本流を辿ると、やがてフィナーレである石積堰堤が上に望める、最後の8m滝へ。
↑ 最後の8m滝
直登は難しいので、右岸巻き。
↑ 左岸巻き
滝上からは残置ロープで下降、沢へ戻ります。
↑ 残置ロープあります
ゴールの目印とされるのが、半壊した石積堰堤。
↑ 石積堰堤がゴール
昭和30年代に壊れたとされる堰堤で、まるで古代遺跡のようなインパクトがあります。
自然界に存在する人工物には本来興味がないのですが、これだけ深い山のなかにこれだけ年数の経ったものが置き去りにされていると、不思議なロマンを感じてしまいました。
堰堤を潜ると、その先は今までとはまるで別世界の明るい広河原。
長くゴルジュのなかを歩いてきたので、広い空と深い緑が目に沁みます。
↑ 広河原
遡行終了点は、東沢出合にある石積堰堤。
↑ 遡行終了点が見えました
ちなみに、東沢出合から右岸に上がると欅平とよばれる平地が広がります。
もしも機会があれば一晩ゆっくりと焚き火を囲みたいところでもあります。
帰路は仲ノ沢径路を辿ります。
この道は昔地元の方が欅平のワサビ田や植林のために行き来した作業道で、本来登山道ではないようです。
植林のなか山腹をトラバースしていくルートなので格別風情はありませんが、踏み跡は極めて明瞭で、小川谷遡行のみならずモチコシ沢遡行などの下山路として沢ヤ御用達になっている感があります。
小川谷廊下は何度訪れても楽しめる素晴らしい美渓。
清流と戯れるだけで心が潤され、まるで童心に帰ったような気にさせられます。
とても水量豊富で、ダイナミックかつ変化に富んだ渓であるだけでなく、適度な遡行時間と難易度、そしてアプローチが比較的便利で、厄介な詰めもなく、帰路の登山道も明瞭です。
首都圏日帰りの沢としては、まさに第一級のもの。
初級者に沢登りの楽しさを知ってもらうのに最適な渓であるだけでなく、大きな遡行を控えたベテランがトレーニングで訪れるのにも適していると思われます。
目的はどうあれ、いつまでも多くの方が楽しめる渓として、その美しさを失わないでいてほしいものです。
今回帰りの立ち寄り湯は、町立中川温泉ぶなの湯。
武田信玄の隠し湯といわれる西丹沢定番の温泉です。
ぶなの湯(月曜休)の情報はこちらをご覧ください
最後までご一読いただき、有難うございました。
※ 画像サイズはスマートフォンで見やすい大きさに設定してあります。
フォトギャラリー
・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。
・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。